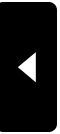2021年09月17日
授乳中の不快感
こんにちは しんしろ助産所です
産後間もないママから、
授乳中に胸がざわざわするような不快感や、
つらい気分になると相談を受けた事があります。
産後はホルモンバランスの変化で身体だけでなく、
精神的にもダメージを受けやすい為なのかと
心配されいていました。
ただ赤ちゃんはおとなしく、良く飲み良く寝る子で
精神的なダメージに心当たりは無いようでした。
授乳時の不快感や気分の落ち込みの原因の一つに
『不快性射乳反射=D-MER:ディーマー』と
呼ばれているものがあります。
これは、母乳育児中の母親の射乳反射の30秒~90秒前に
胃の不快感、不安、悲しみ、恐怖、気分の落ち込み、
緊張、感情的な動揺、イライラ、絶望感、
否定的な感情が現れ、射乳反射のたびに繰り返される
不快症状の事を言います。
個人の成育歴や分娩の体験などは影響しないようです。
ドーパミンが介在する事はわかっていますが
不快感そのものは母親自身しかわからないため、


産後間もないママから、
授乳中に胸がざわざわするような不快感や、
つらい気分になると相談を受けた事があります。
産後はホルモンバランスの変化で身体だけでなく、
精神的にもダメージを受けやすい為なのかと
心配されいていました。
ただ赤ちゃんはおとなしく、良く飲み良く寝る子で
精神的なダメージに心当たりは無いようでした。
授乳時の不快感や気分の落ち込みの原因の一つに
『不快性射乳反射=D-MER:ディーマー』と
呼ばれているものがあります。
これは、母乳育児中の母親の射乳反射の30秒~90秒前に
胃の不快感、不安、悲しみ、恐怖、気分の落ち込み、
緊張、感情的な動揺、イライラ、絶望感、
否定的な感情が現れ、射乳反射のたびに繰り返される
不快症状の事を言います。
個人の成育歴や分娩の体験などは影響しないようです。
ドーパミンが介在する事はわかっていますが
症状が出る方と出ない方がおり、その理由はわかっていません
不快性射乳反射は、ホルモンによる反射で起こるため、
自分自身でコントロールする事は出来ません。
通常は産後数ヶ月で落ち着く事が多いと言われますが、
中には授乳期間中続く場合もあり、個人差が大きいと言われます。

不快性射乳反射は、ホルモンによる反射で起こるため、
自分自身でコントロールする事は出来ません。
通常は産後数ヶ月で落ち着く事が多いと言われますが、
中には授乳期間中続く場合もあり、個人差が大きいと言われます。
不快感そのものは母親自身しかわからないため、
本当に不快性射乳反射かどうかを
自分で判断するのはなかなか難しいと思います。
不快感が強く出る、授乳する事が憂鬱で仕方がない
といった場合は、早めに病院などで相談してみて下さいね
といった場合は、早めに病院などで相談してみて下さいね


2021年09月14日
お風呂での授乳
こんにちは しんしろ助産所です
母乳育児中、
「お風呂でおっぱいを飲ませたことがある」
というママはみえるのではないでしょうか。
一緒にお風呂に入ると、
大好きなおっぱいが目の前にあることに気づいて
飲みたがるようになるのでしょうね。
「これってうちだけ・・・?」
と心配される方もみえますが
意外とよくあることです。
個人差はありますが、
生後6か月頃からみられるようになってきます。
おふろでおっぱいを飲むことには
賛否両論あるかもしれません。
お風呂でおっぱいを飲むなんて行儀が悪い
お風呂で飲む必要はない
おっぱいを見たら欲しがるのは自然なこと
ママと子どもの絆がさらに深まる
など。
“お風呂で飲ませる方がいい” というわけでもなければ
“飲ませてはいけない” という決まりもないので
ママの気持ち次第でいいのかなと思います。
おっぱいは赤ちゃんにとって
食事、水分補給だけでなく
精神安定剤の役割もあります。
おっぱいもいつか卒業するように
お風呂での授乳もいつまでも続くわけではありません。
欲しがるからあげてたけど
なんとなくダメなことなのかと思ってた、とか
自分だけなのかと心配していたというママは
安心して続けてあげてくださいね。
お風呂では飲ませたくないのに困っている・・・
というママは
●Tシャツやタンクトップを着て、
おっぱいを見せないようにする
●お風呂で遊べるおもちゃなどで気をそらす
●お風呂上がってからね~と言い聞かせる
といった対応をしてみましょう。
ママと赤ちゃんにとってよいと思われる方法を
選んでくださいね

母乳育児中、
「お風呂でおっぱいを飲ませたことがある」
というママはみえるのではないでしょうか。
一緒にお風呂に入ると、
大好きなおっぱいが目の前にあることに気づいて
飲みたがるようになるのでしょうね。
「これってうちだけ・・・?」
と心配される方もみえますが
意外とよくあることです。
個人差はありますが、
生後6か月頃からみられるようになってきます。
おふろでおっぱいを飲むことには
賛否両論あるかもしれません。
お風呂でおっぱいを飲むなんて行儀が悪い

お風呂で飲む必要はない

おっぱいを見たら欲しがるのは自然なこと

ママと子どもの絆がさらに深まる

など。
“お風呂で飲ませる方がいい” というわけでもなければ
“飲ませてはいけない” という決まりもないので
ママの気持ち次第でいいのかなと思います。
おっぱいは赤ちゃんにとって
食事、水分補給だけでなく
精神安定剤の役割もあります。
おっぱいもいつか卒業するように
お風呂での授乳もいつまでも続くわけではありません。
欲しがるからあげてたけど
なんとなくダメなことなのかと思ってた、とか
自分だけなのかと心配していたというママは
安心して続けてあげてくださいね。
お風呂では飲ませたくないのに困っている・・・
というママは
●Tシャツやタンクトップを着て、
おっぱいを見せないようにする
●お風呂で遊べるおもちゃなどで気をそらす
●お風呂上がってからね~と言い聞かせる
といった対応をしてみましょう。
ママと赤ちゃんにとってよいと思われる方法を
選んでくださいね

2021年06月11日
母乳パッド
こんにちは しんしろ助産所です
母乳育児のアイテムの一つ「母乳パッド 」
」
産後の乳首を保護しつつ、母乳の漏れを防ぐものです。
母乳パッドには紙製、布製があり、
それぞれに特徴があります。
【紙製】
・使い捨てタイプ
・頻繁な授乳や母乳分泌量が多いママにおすすめ
・1枚ずつの個包装のもの、2枚1組ずつの包装のものがある
・肌ざわり、吸収性、ムレにくさ、ズレにくさなど メーカーによって違いがある
【布製】
・100%オーガニックコットン使用のものなどもある
・肌が弱いママにはおすすめ
・吸収力も高い
・メーカーによってはサイズがあるものも
・紙に比べ形がしっかりしている
・洗って繰り返し使用できる
どちらがいいのかはママ次第。
布製は最初は購入金額が高くなりますが
授乳経験のあるママさんに聞いたり、サンプルを見たりして
自分に合うものを探してくださいね

母乳育児のアイテムの一つ「母乳パッド
 」
」産後の乳首を保護しつつ、母乳の漏れを防ぐものです。
母乳パッドには紙製、布製があり、
それぞれに特徴があります。
【紙製】
・使い捨てタイプ
・頻繁な授乳や母乳分泌量が多いママにおすすめ
・1枚ずつの個包装のもの、2枚1組ずつの包装のものがある
・肌ざわり、吸収性、ムレにくさ、ズレにくさなど メーカーによって違いがある
【布製】
・100%オーガニックコットン使用のものなどもある
・肌が弱いママにはおすすめ
・吸収力も高い
・メーカーによってはサイズがあるものも
・紙に比べ形がしっかりしている
・洗って繰り返し使用できる
どちらがいいのかはママ次第。
布製は最初は購入金額が高くなりますが
洗って繰り返し使えるので経済的にも環境にもベスト
ただ母乳の分泌が多いママは頻繁に交換が必要となるため
使い捨ても便利です。
ただ母乳の分泌が多いママは頻繁に交換が必要となるため
使い捨ても便利です。
選択するポイントとしては
・肌質に合うもの
・常に清潔な状態に保てるもの です。
・肌質に合うもの
・常に清潔な状態に保てるもの です。
紙製にしても布製にしても
使用している素材はメーカーごとに違うので
ママの肌質や状態によって合う、合わないということも。
実際には使ってみないとわからないことがあるので
お試しなどで利用してみるのもいいですね。
母乳分泌の様子も見ながら
実際には使ってみないとわからないことがあるので
お試しなどで利用してみるのもいいですね。
母乳分泌の様子も見ながら
産後に買い足していけばいいと思います。
授乳経験のあるママさんに聞いたり、サンプルを見たりして
自分に合うものを探してくださいね

2021年04月22日
母乳の出が悪くなった・・・?
こんにちは しんしろ助産所です
「最近母乳の出が悪くなった感じがする 」
」
と相談にみえるママは多くみえます。
どうして母乳の出が悪くなったと
感じたのか伺ってみると、
「おっぱいが張らなくなった」
「頻繁におっぱいをほしがるようになった」
「よくぐずって泣く」
「おっぱいを長い時間吸うようになった」
「以前よりあまり飲んでくれなくなった」
など
これって本当に母乳の出が悪くなったのでしょうか?
おっぱいが張らなくなった
→ 出産後数日経って母乳が作られ始める頃は
おっぱいが張ってきますが、数週間経つと、
赤ちゃんが吸う刺激で反射が起こり、
母乳が湧き出すように変わってきます。
そのため、授乳間隔があけば張るけれど
いつもの間隔で授乳をしていれば
張りは落ち着いてくることが多いです。
張らなくなった=母乳の出が悪くなった
というわけではありません。
頻繁におっぱいをほしがる、ぐずる、長い時間吸う
→ 赤ちゃんには急成長期と言われる時期が
何度かあります。(生後3週頃、6週頃、3か月頃)
欲しがるのに合わせて授乳していると
数日~1週間ほどで母乳量も増え、
落ち着いてきます。
頻繁に欲しがる、ぐずる、長い時間吸う=出が悪くなった
というわけではありません。
あまり飲んでくれない
→ 頻繁に欲しがるのとは逆に
すぐにおっぱいを離してしまったり、
集中して飲んでくれないと
「出ていないから?」と心配になってしまいますね。
生後3~4か月頃には周りが気になって
授乳に集中できない時期があります。
実際に、哺乳量や体重測定をしてみると
いずれも順調で母乳の分泌も
問題ない方がみえます。
ただ、なかには体重の増えが少なく、
哺乳量も少なくなり、母乳の出が悪くなっている方も・・・
母乳の出が悪くなるのは
ストレスや睡眠不足、疲労なども関係しますが
多くは、ミルクを足す量が多い、
赤ちゃんがうまく飲んでくれない、
授乳回数が減ったなど、
おっぱいへの刺激が減ることで起こります。
哺乳量測定や体重測定とともに
授乳状況をお聞きし、
授乳の様子を見させていただくことで
本当に母乳の出が悪くなっているのか、
また、原因は何か分かることもあります。
心配なときは一人で悩まず
早めにご相談くださいね

「最近母乳の出が悪くなった感じがする
 」
」と相談にみえるママは多くみえます。
どうして母乳の出が悪くなったと
感じたのか伺ってみると、
「おっぱいが張らなくなった」
「頻繁におっぱいをほしがるようになった」
「よくぐずって泣く」
「おっぱいを長い時間吸うようになった」
「以前よりあまり飲んでくれなくなった」
など
これって本当に母乳の出が悪くなったのでしょうか?
おっぱいが張らなくなった
→ 出産後数日経って母乳が作られ始める頃は
おっぱいが張ってきますが、数週間経つと、
赤ちゃんが吸う刺激で反射が起こり、
母乳が湧き出すように変わってきます。
そのため、授乳間隔があけば張るけれど
いつもの間隔で授乳をしていれば
張りは落ち着いてくることが多いです。
張らなくなった=母乳の出が悪くなった
というわけではありません。
頻繁におっぱいをほしがる、ぐずる、長い時間吸う
→ 赤ちゃんには急成長期と言われる時期が
何度かあります。(生後3週頃、6週頃、3か月頃)
欲しがるのに合わせて授乳していると
数日~1週間ほどで母乳量も増え、
落ち着いてきます。
頻繁に欲しがる、ぐずる、長い時間吸う=出が悪くなった
というわけではありません。
あまり飲んでくれない
→ 頻繁に欲しがるのとは逆に
すぐにおっぱいを離してしまったり、
集中して飲んでくれないと
「出ていないから?」と心配になってしまいますね。
生後3~4か月頃には周りが気になって
授乳に集中できない時期があります。
実際に、哺乳量や体重測定をしてみると
いずれも順調で母乳の分泌も
問題ない方がみえます。
ただ、なかには体重の増えが少なく、
哺乳量も少なくなり、母乳の出が悪くなっている方も・・・
母乳の出が悪くなるのは
ストレスや睡眠不足、疲労なども関係しますが
多くは、ミルクを足す量が多い、
赤ちゃんがうまく飲んでくれない、
授乳回数が減ったなど、
おっぱいへの刺激が減ることで起こります。
哺乳量測定や体重測定とともに
授乳状況をお聞きし、
授乳の様子を見させていただくことで
本当に母乳の出が悪くなっているのか、
また、原因は何か分かることもあります。
心配なときは一人で悩まず
早めにご相談くださいね

2021年04月08日
おっぱいでむせる赤ちゃん
こんにちは しんしろ助産所です
授乳中、赤ちゃんが急にむせてしまって
びっくりしたことがある方は
多いのではないでしょうか。
顔を真っ赤にしてゴホゴホと苦しそうで
そんな様子が何度もあったりすると
心配になってしまいますね
赤ちゃんがむせてしまうのは
多くは母乳の分泌がよく、
射乳反射が起きて勢いよく母乳が出るとき、
また、泣いて興奮気味のときや
ウトウト眠りがちのときなどに見られます。
むせても、少し落ち着いたら
またすぐに飲み始める子も多いですが、
なかには泣いて怒ったり、
飲むのをやめてしまう子もいます。
「肺炎になったりしない?」
と心配されることもありますが
健康な赤ちゃんであれば
おっぱいでむせて肺炎になることは
滅多にありません。
なるべくむせないようにするには・・・
●射乳反射が起き、母乳が勢いよく出る時は
一度赤ちゃんの口を外し、タオルなどで受け
反射が落ち着いてから授乳を再開する
●ママがソファや座椅子などに
もたれかかるような姿勢で授乳すると
口に入る勢いが和らいでむせにくくなるそう。
●興奮気味の赤ちゃんはなだめてから授乳する。
それでも、むせてしまったときは
一度縦抱きにして背中をトントンしたりさすったりして
落ち着かせてあげるようにしましょう。
初めのうちはむせることが多かった赤ちゃんも
成長とともに勢いよく出るおっぱいにも
上手に対応できるようになり、
むせることも少なくなってきます。
できる対応をしながら成長を見守ってあげましょう。

授乳中、赤ちゃんが急にむせてしまって
びっくりしたことがある方は
多いのではないでしょうか。
顔を真っ赤にしてゴホゴホと苦しそうで
そんな様子が何度もあったりすると
心配になってしまいますね

赤ちゃんがむせてしまうのは
多くは母乳の分泌がよく、
射乳反射が起きて勢いよく母乳が出るとき、
また、泣いて興奮気味のときや
ウトウト眠りがちのときなどに見られます。
むせても、少し落ち着いたら
またすぐに飲み始める子も多いですが、
なかには泣いて怒ったり、
飲むのをやめてしまう子もいます。
「肺炎になったりしない?」
と心配されることもありますが
健康な赤ちゃんであれば
おっぱいでむせて肺炎になることは
滅多にありません。
なるべくむせないようにするには・・・
●射乳反射が起き、母乳が勢いよく出る時は
一度赤ちゃんの口を外し、タオルなどで受け
反射が落ち着いてから授乳を再開する
●ママがソファや座椅子などに
もたれかかるような姿勢で授乳すると
口に入る勢いが和らいでむせにくくなるそう。
●興奮気味の赤ちゃんはなだめてから授乳する。
それでも、むせてしまったときは
一度縦抱きにして背中をトントンしたりさすったりして
落ち着かせてあげるようにしましょう。
初めのうちはむせることが多かった赤ちゃんも
成長とともに勢いよく出るおっぱいにも
上手に対応できるようになり、
むせることも少なくなってきます。
できる対応をしながら成長を見守ってあげましょう。
2021年02月26日
授乳日誌
こんにちは しんしろ助産所です
しんしろ助産所では、母乳育児を応援 しています。
しています。
授乳日誌を見せてもらうと、哺乳や補足量、排泄の状況などがわかるため、
「母乳育児が上手くいっているかどうか」
以前見せてもらったのは、パパ自作のもの。

しんしろ助産所では、母乳育児を応援
 しています。
しています。退院後、2週間健診や母乳相談などで
対応してくれる施設が多くなりましたが、
対応してくれる施設が多くなりましたが、
授乳後に赤ちゃんが泣いたり、回数が頻回だったりすると
「母乳が足りないのでは??」
という不安がよぎる方は大勢みえます。
「おっぱいがどのくらい飲めているの」
「うまくおっぱいを吸わせられない」
「おっぱいの量を増やしたい」
「体重は増えているのかな」
「おっぱいの量を増やしたい」
「体重は増えているのかな」
など、ママの心配は尽きません

そんな時、重宝するのは授乳日誌

来所される方の中には、哺乳量が不足していたり、
逆にミルクの補足のしすぎなどの赤ちゃんもいます。
授乳日誌を見せてもらうと、哺乳や補足量、排泄の状況などがわかるため、
「母乳育児が上手くいっているかどうか」
「授乳回数を増やす場合にはどの時間帯に増やせるだろうか…」
など具体的な提案もできます。
実際に、赤ちゃんがどのくらい飲んでいるのか計測したり、
おっぱいの飲ませ方や含ませ方、抱っこの仕方等を
一緒に確認すると、さらにわかりやすいと思います。
おっぱいの飲ませ方や含ませ方、抱っこの仕方等を
一緒に確認すると、さらにわかりやすいと思います。
授乳日誌には色々な形式があり、
成長発達や育児の記録を記載できるものもあります。
記入方法も人それぞれで、
スマホのアプリに入力している方もいれば、
市販の日誌を利用する方、
自分なりにノートに記載している方等々、さまざまな形があります。
以前見せてもらったのは、パパ自作のもの。
パソコンで作ってありました。
赤ちゃんの哺乳状況、成長などが手に取るようにわかる、
世界に一つだけの日誌ですね

記録として参考になるだけでなく、
あとから見るとその場面が思い出され、
なつかしさや愛おしさを感じます。
赤ちゃんが生まれ、毎日の生活、育児で
忙しい毎日ですが、授乳日誌をつけてみませんか?
なつかしさや愛おしさを感じます。
赤ちゃんが生まれ、毎日の生活、育児で
忙しい毎日ですが、授乳日誌をつけてみませんか?
2021年02月18日
夜間断乳
こんにちは しんしろ助産所です
いつの頃からか耳にするようになった
夜間断乳という考え方。
助産所でも時々お母さん達から
「夜間断乳しました」
と聞いたり、
「どうやってやるの?」
「やった方がいいの?」
と聞かれることがあります。
夜間断乳は文字通り、
日中の授乳はいつも通りに行い、
夜間の授乳をやめる方法です。
主に、夜間授乳がお母さんにとって
疲労やストレスの原因になっている場合や
本格的な断乳に向けた前段階として
行う方が多いのですが、必ずしも
やらなければいけないことではありません。
夜間に子どもが目を覚ますのは
月齢が進んでくるとお腹がすくというより
眠りが浅くなったときにお母さんを求めるため。
おっぱいを吸って安心すると
また、眠りにつきます。
夜間断乳をするためには、
そうやって夜に目が覚めても授乳をしないこと。
抱っこや背中をトントンしてあやす、
お茶を飲ませる・・・など
授乳以外の方法で対応します。
子どもがギャン泣きをして
お互い眠れないこともあり、
もう授乳してしまおうかと思った
というママの声を聞くこともあります。
本格的な断乳の場合も夜間断乳の場合も
個人差はありますが
多くの子が最初の数日は泣いても
徐々に長く寝るようになってきます。
ただ、なかには相変わらず
何度も目を覚ますという子も・・・
本格的な断乳と比べて
日中は授乳をして夜間だけしない夜間断乳は
子どもが混乱してしまわないかな?
夜間断乳の方が難しいのかな?
とも思いましたが
それも個人差があるようです。
子どもの様子やお母さんの体調、
家庭の事情などに合わせて
ベストだと思う方法を選びたいですね。
悩んだり困ったときは
一人で考え込まずぜひご相談ください

いつの頃からか耳にするようになった
夜間断乳という考え方。
助産所でも時々お母さん達から
「夜間断乳しました」
と聞いたり、
「どうやってやるの?」
「やった方がいいの?」
と聞かれることがあります。
夜間断乳は文字通り、
日中の授乳はいつも通りに行い、
夜間の授乳をやめる方法です。
主に、夜間授乳がお母さんにとって
疲労やストレスの原因になっている場合や
本格的な断乳に向けた前段階として
行う方が多いのですが、必ずしも
やらなければいけないことではありません。
夜間に子どもが目を覚ますのは
月齢が進んでくるとお腹がすくというより
眠りが浅くなったときにお母さんを求めるため。
おっぱいを吸って安心すると
また、眠りにつきます。
夜間断乳をするためには、
そうやって夜に目が覚めても授乳をしないこと。
抱っこや背中をトントンしてあやす、
お茶を飲ませる・・・など
授乳以外の方法で対応します。
子どもがギャン泣きをして
お互い眠れないこともあり、
もう授乳してしまおうかと思った

というママの声を聞くこともあります。
本格的な断乳の場合も夜間断乳の場合も
個人差はありますが
多くの子が最初の数日は泣いても
徐々に長く寝るようになってきます。
ただ、なかには相変わらず
何度も目を覚ますという子も・・・
本格的な断乳と比べて
日中は授乳をして夜間だけしない夜間断乳は
子どもが混乱してしまわないかな?
夜間断乳の方が難しいのかな?
とも思いましたが
それも個人差があるようです。
子どもの様子やお母さんの体調、
家庭の事情などに合わせて
ベストだと思う方法を選びたいですね。
悩んだり困ったときは
一人で考え込まずぜひご相談ください

2021年01月28日
授乳が不快? D-MER
こんにちは しんしろ助産所です
授乳をすると、その刺激で
分泌されるオキシトシンというホルモンが
別名愛情ホルモン、幸せホルモン と言われるのを
と言われるのを
聞いたことがある方も多いと思います。
そのため、授乳をすると
赤ちゃんをかわいいと思えたり、
幸福感を感じたり、
いろいろなストレスから
お母さんを守ってくれるとも言われます。
ただ、なかには
授乳をすると逆に、不安や焦り、イライラ、
気持ち悪い といった不快感を
といった不快感を
感じてしまう人もいるのだそうです。
これを D-MER(不快性射乳反射)と言います。
D-MERの方の多くは
授乳をして嫌な気分になってしまう自分に
赤ちゃんへの愛情がないの?
母親失格?
と悩んでしまいがちですが
決してそんなことはありません。
D-MERもまた、授乳によるホルモンの
変化で起こる現象です。
授乳時に、母乳を作るプロラクチンの
血中濃度を上げるため、ドーパミン値が
一時的に下がることが関係しているのだそう。
自分の意思とは関係なく
起こってしまうものなので
自分を責めなくても大丈夫!

授乳をすると、その刺激で
分泌されるオキシトシンというホルモンが
別名愛情ホルモン、幸せホルモン
 と言われるのを
と言われるのを聞いたことがある方も多いと思います。
そのため、授乳をすると
赤ちゃんをかわいいと思えたり、
幸福感を感じたり、
いろいろなストレスから
お母さんを守ってくれるとも言われます。
ただ、なかには
授乳をすると逆に、不安や焦り、イライラ、
気持ち悪い
 といった不快感を
といった不快感を感じてしまう人もいるのだそうです。
これを D-MER(不快性射乳反射)と言います。
D-MERの方の多くは
授乳をして嫌な気分になってしまう自分に
赤ちゃんへの愛情がないの?
母親失格?
と悩んでしまいがちですが
決してそんなことはありません。
D-MERもまた、授乳によるホルモンの
変化で起こる現象です。
授乳時に、母乳を作るプロラクチンの
血中濃度を上げるため、ドーパミン値が
一時的に下がることが関係しているのだそう。
自分の意思とは関係なく
起こってしまうものなので
自分を責めなくても大丈夫!
個人差はありますが
授乳のうちの数分だけ
産後3か月頃になると落ち着くことが多い
とも言われます。
対処法として
スマホやテレビを見て気を紛らわす
のもいいよう。
どうしても無理!というときには
ミルクに頼る選択肢もあります。
まだあまり知られていないD-MER。
原因がわからず悩んでいるママも
みえるかもしれません。
原因を知って、自分を責めるママが
一人でも減りますように
2020年12月15日
乳腺炎
こんにちは しんしろ助産所です
産後のトラブルの一つである「乳腺炎」。
乳腺炎には大きく分けて
「うっ滞性」「感染性」の2種類があります。
症状は一般的に
●発熱
●乳房のしこり
●痛み
●乳房の発赤・熱感 など。
まずは「うっ滞性」を疑い、
●効果的に赤ちゃんに飲み取ってもらう
●搾乳および乳房ケア
等をおこなうことで、改善を目指します。
改善が見られず、症状が24時間以上経過する場合は
引き続き上記をおこないながら
「感染性」を疑い、医師の診察を勧めます。
「乳腺炎」と聞くと
「搾ってもらえば治る」と思いがちですが
「感染性」の場合は授乳や乳房ケアのみでの回復は困難です。
おっぱいを空にすることと並行して
医師に診断および治療の必要性を判断してもらい、
早期に改善を試みる必要があります。
この時期、発熱すると風邪やインフルエンザ、
加えて今はコロナの感染も疑われます。
時々「体の節々が痛み、熱があり、頭が痛い。
そういえばおっぱいも痛むような気がする。」
という相談の電話を受けます。
乳腺炎の場合、
おっぱいの違和感や痛み、しこりなどが主症状です。
乳房の痛みやしこりが明らかでなく
主な症状が熱やその他の場合は、
熱により乳房全体が張って
違和感を感じていることもあります。
マスク等で赤ちゃんへの飛沫を避けた上で
しっかり飲み取ってもらいましょう。
その上でおっぱいに違和感が続くようなら
まずはお電話でご相談ください

産後のトラブルの一つである「乳腺炎」。
乳腺炎には大きく分けて
「うっ滞性」「感染性」の2種類があります。
症状は一般的に
●発熱
●乳房のしこり
●痛み
●乳房の発赤・熱感 など。
まずは「うっ滞性」を疑い、
●効果的に赤ちゃんに飲み取ってもらう
●搾乳および乳房ケア
等をおこなうことで、改善を目指します。
改善が見られず、症状が24時間以上経過する場合は
引き続き上記をおこないながら
「感染性」を疑い、医師の診察を勧めます。
「乳腺炎」と聞くと
「搾ってもらえば治る」と思いがちですが
「感染性」の場合は授乳や乳房ケアのみでの回復は困難です。
おっぱいを空にすることと並行して
医師に診断および治療の必要性を判断してもらい、
早期に改善を試みる必要があります。
この時期、発熱すると風邪やインフルエンザ、
加えて今はコロナの感染も疑われます。
時々「体の節々が痛み、熱があり、頭が痛い。
そういえばおっぱいも痛むような気がする。」
という相談の電話を受けます。
乳腺炎の場合、
おっぱいの違和感や痛み、しこりなどが主症状です。
乳房の痛みやしこりが明らかでなく
主な症状が熱やその他の場合は、
熱により乳房全体が張って
違和感を感じていることもあります。
マスク等で赤ちゃんへの飛沫を避けた上で
しっかり飲み取ってもらいましょう。
その上でおっぱいに違和感が続くようなら
まずはお電話でご相談ください

2020年10月12日
卒乳に悩んだら
こんにちは しんしろ助産所です
母乳に関する相談はたくさんありますが
その中に「卒乳」についての相談もあります。
一言で「卒乳」といっても種類もいろいろ。
●児の方から自然に母乳を飲まなくなる
「自然卒乳(いわゆる卒乳)」
●医学的な理由で母乳をやめる必要がある、
職場復帰をしたい…などの場合に、ある時期を見据えて

母乳に関する相談はたくさんありますが
その中に「卒乳」についての相談もあります。
一言で「卒乳」といっても種類もいろいろ。
●児の方から自然に母乳を飲まなくなる
「自然卒乳(いわゆる卒乳)」
●医学的な理由で母乳をやめる必要がある、
職場復帰をしたい…などの場合に、ある時期を見据えて
1日の授乳回数などをゆっくり減らしていく方法
「計画的卒乳」
●仕事の都合で日中の授乳をやめるなど
授乳の一部だけをやめる方法
「部分的卒乳」
●まだ授乳回数や量が多いが
授乳をストップして母乳を止める方法
「急激な卒乳(いわゆる断乳)」
近年は児が主体的に母乳を欲しがらなくなる
「自然卒乳」が理想とされているためか、
それ以外の理由で卒乳を決意したママたちは
言いにくそうに、申し訳なさそうに切り出す方が
多いような気がします。
「卒乳」を希望する場合には
必ず理由を聞くようにしています。
「不妊治療の受精卵の期限があるので…」
「おっぱいをかまれるので 痛くて辛いです 」
」
「妊娠がわかったので」
みなさん理由はさまざま。
悩んで決心したことを責めるつもりで
聞いているのではありません。
中には、本当は授乳を続けたいのに
「『まだ飲ませてるの?』と聞かれるので」
「周りがみんなおっぱいをやめたので 焦ってます」
「1歳過ぎたらやめるのが普通ですよね?」
「最近母乳を泣いて拒否するようになってしまって 」
」
という理由で卒乳を決心される方がいるからです。
話しを聞いた上で、
やめなくても良い理由や無理のない方法を伝えると
「もう少し続けてみます 」
」
と笑顔で帰って行かれる方もみえます。
卒乳をしようか迷って見える方、
まずは一度ご相談ください
「計画的卒乳」
●仕事の都合で日中の授乳をやめるなど
授乳の一部だけをやめる方法
「部分的卒乳」
●まだ授乳回数や量が多いが
授乳をストップして母乳を止める方法
「急激な卒乳(いわゆる断乳)」
近年は児が主体的に母乳を欲しがらなくなる
「自然卒乳」が理想とされているためか、
それ以外の理由で卒乳を決意したママたちは
言いにくそうに、申し訳なさそうに切り出す方が
多いような気がします。
「卒乳」を希望する場合には
必ず理由を聞くようにしています。
「不妊治療の受精卵の期限があるので…」
「おっぱいをかまれるので 痛くて辛いです
 」
」「妊娠がわかったので」
みなさん理由はさまざま。
悩んで決心したことを責めるつもりで
聞いているのではありません。
中には、本当は授乳を続けたいのに
「『まだ飲ませてるの?』と聞かれるので」
「周りがみんなおっぱいをやめたので 焦ってます」
「1歳過ぎたらやめるのが普通ですよね?」
「最近母乳を泣いて拒否するようになってしまって
 」
」という理由で卒乳を決心される方がいるからです。
話しを聞いた上で、
やめなくても良い理由や無理のない方法を伝えると
「もう少し続けてみます
 」
」と笑顔で帰って行かれる方もみえます。
卒乳をしようか迷って見える方、
まずは一度ご相談ください

2020年10月08日
おっぱいで寝かしつけるのはよくない?
こんにちは しんしろ助産所です
赤ちゃんが
おっぱいを飲みながらウトウト・・・
そのまま寝落ちしてしまうことはよくあることです。
授乳は赤ちゃんにとって
おなかも心も満たされる至福のひととき
気持ちよくなって、そのまま
眠りにつくのもわかります。
そうしているうちに、
“寝かしつけるときにはおっぱいを飲みながら”
が習慣になることもよくあるものです。
時々
「おっぱいで寝かしつけるのはよくない?」
と心配されるママの声を聞きます。
そんなことはありません。
おっぱいでの寝かしつけは
ママにとっても楽で
赤ちゃんにとっても安心して眠りにつけるもの。
おっぱい以外の方法で
寝かしつけようと思ったら
赤ちゃんはグズグズ 、ママはイライラ
、ママはイライラ して
して
なかなかうまくいかないことも多いものです。
でも、
「このままおっぱいなしでは
寝られなくなったらどうしよう・・・」
「ママでないと寝かしつけられない?」
「歯が生え始めたら虫歯のリスクは?」
といったことを心配されることが
多いように思います。
また、最近では
寝かしつけにもいろいろな考え方があり、
どうするのがよいのか
悩んでしまうこともあるかもしれません。
おっぱいでの寝かしつけは
成長とともに
徐々に授乳回数が減ってくると
他の方法でも寝るようになる子もいれば
卒乳までおっぱいで寝る子もいます。
でも、いつかはおっぱいがなくても
寝るようになります。
また、ママでないと寝られない子もいれば、
ママと寝るときはおっぱいがほしいけど
パパとならそうでなくても寝られる子もいます。
虫歯のリスクについてはこちらを
参考にしてみてください。
ママも赤ちゃんも
家庭の状況もそれぞれ違います。
こうでなきゃ!というきまりはなく、
いろいろな形があっていいものだと思います。
ママや赤ちゃんにとって
ストレスや負担のない方法を選べるといいですね

赤ちゃんが
おっぱいを飲みながらウトウト・・・

そのまま寝落ちしてしまうことはよくあることです。
授乳は赤ちゃんにとって
おなかも心も満たされる至福のひととき

気持ちよくなって、そのまま
眠りにつくのもわかります。
そうしているうちに、
“寝かしつけるときにはおっぱいを飲みながら”
が習慣になることもよくあるものです。
時々
「おっぱいで寝かしつけるのはよくない?」
と心配されるママの声を聞きます。
そんなことはありません。
おっぱいでの寝かしつけは
ママにとっても楽で
赤ちゃんにとっても安心して眠りにつけるもの。
おっぱい以外の方法で
寝かしつけようと思ったら
赤ちゃんはグズグズ
 、ママはイライラ
、ママはイライラ して
してなかなかうまくいかないことも多いものです。
でも、
「このままおっぱいなしでは
寝られなくなったらどうしよう・・・」
「ママでないと寝かしつけられない?」
「歯が生え始めたら虫歯のリスクは?」
といったことを心配されることが
多いように思います。
また、最近では
寝かしつけにもいろいろな考え方があり、
どうするのがよいのか
悩んでしまうこともあるかもしれません。
おっぱいでの寝かしつけは
成長とともに
徐々に授乳回数が減ってくると
他の方法でも寝るようになる子もいれば
卒乳までおっぱいで寝る子もいます。
でも、いつかはおっぱいがなくても
寝るようになります。
また、ママでないと寝られない子もいれば、
ママと寝るときはおっぱいがほしいけど
パパとならそうでなくても寝られる子もいます。
虫歯のリスクについてはこちらを
参考にしてみてください。
ママも赤ちゃんも
家庭の状況もそれぞれ違います。
こうでなきゃ!というきまりはなく、
いろいろな形があっていいものだと思います。
ママや赤ちゃんにとって
ストレスや負担のない方法を選べるといいですね

2020年06月03日
おっぱいを飲みながら指しゃぶりする赤ちゃん
こんにちは しんしろ助産所です
生後3ヶ月を過ぎた頃から
おっぱいを飲んでいるときに
隙間から自分の指を口に入れて
おっぱいと指を一緒に吸おうとする
赤ちゃんが時々います。
その様子に
「おっぱいより指の方がいいの~ 」
」
と心配になってしまうママもみえます。
生後3ヶ月頃といえば
自分の手をじーっと見つめたり、
それを口に持っていっては
ちゅぱちゅぱとくわえて遊んだり、
そのうち、指を吸ったりするようになる時期。
自分の「手」の存在に気づき、
口に運んで確かめるようになるのですね。
授乳中の指しゃぶりは
この癖がつい授乳中にも出てしまっている場合や
このくらいの時期からよく見られる遊び飲みの一種、
また、歯の生え始めで口の中が気になるとき
などが考えられます。
授乳し始めてすぐやる子もいれば、
おなかが満たされて集中が途切れるためか、
授乳し始めてしばらくしてからやる子もいます。
指しゃぶりをしながら飲んでいると
集中して飲めず、十分な量が飲めないままになったり、
吸いつきが浅くなって乳頭に痛みを感じたり、
トラブルの元になってしまうことも・・・
そのため、授乳中に指を口にもっていったときは
そっと手を握ってあげましょう。
それだけでちゃんとおっぱいを飲んでくれる子も多いものです。
おなかが満たされて遊んでいるようなら
授乳を切り上げてしまうのもひとつ。
遊び飲みをして授乳に集中できないときは
以前のブログ 授乳中に気が散る赤ちゃん
歯の生え始めかも・・・というときは
歯の生えはじめのむず痒さ

生後3ヶ月を過ぎた頃から
おっぱいを飲んでいるときに
隙間から自分の指を口に入れて
おっぱいと指を一緒に吸おうとする
赤ちゃんが時々います。
その様子に
「おっぱいより指の方がいいの~
 」
」と心配になってしまうママもみえます。
生後3ヶ月頃といえば
自分の手をじーっと見つめたり、
それを口に持っていっては
ちゅぱちゅぱとくわえて遊んだり、
そのうち、指を吸ったりするようになる時期。
自分の「手」の存在に気づき、
口に運んで確かめるようになるのですね。
授乳中の指しゃぶりは
この癖がつい授乳中にも出てしまっている場合や
このくらいの時期からよく見られる遊び飲みの一種、
また、歯の生え始めで口の中が気になるとき
などが考えられます。
授乳し始めてすぐやる子もいれば、
おなかが満たされて集中が途切れるためか、
授乳し始めてしばらくしてからやる子もいます。
指しゃぶりをしながら飲んでいると
集中して飲めず、十分な量が飲めないままになったり、
吸いつきが浅くなって乳頭に痛みを感じたり、
トラブルの元になってしまうことも・・・
そのため、授乳中に指を口にもっていったときは
そっと手を握ってあげましょう。
それだけでちゃんとおっぱいを飲んでくれる子も多いものです。
おなかが満たされて遊んでいるようなら
授乳を切り上げてしまうのもひとつ。
遊び飲みをして授乳に集中できないときは
以前のブログ 授乳中に気が散る赤ちゃん
歯の生え始めかも・・・というときは
歯の生えはじめのむず痒さ
も参考にしてみてくださいね

2020年03月10日
授乳と花粉症
こんにちは しんしろ助産所です
通勤時に桜の花 を見ると春が来ているのを感じます。
を見ると春が来ているのを感じます。
今日は雨ですが、濡れた桜もきれいです。
ただ、巷は新型コロナ感染症の影響で
春のうららかさが少ないのは残念です。
さて、この時期、花粉症で悩まれる方は多くみえます。
特に授乳中のママは普段の薬が使えず
「つらい 」との声が聞こえてきます。
」との声が聞こえてきます。
内服にしても点眼薬にしても添付文書をみると
“授乳を避けること”と記載されています。
授乳を優先すべきか、それとも治療を優先すべきか
悩んでしまいますね。
現在、花粉症の症状を抑える薬はたくさんの種類があります。
内服薬として多く使われるものには抗ヒスタミン剤があります。
第2世代の抗ヒスタミン剤は母乳中に移行する量が少ないものもあり、
内服はしないにしても、点眼薬や点鼻薬を使えるのかと
心配する方もいらっしゃいます。
内服薬と比較すると、点眼薬の使用では、ママの血液中に
吸収される薬の量はごくわずかで問題ないことが多いです。
花粉症の季節も今までと同じように母乳育児を楽しめるといいですね


通勤時に桜の花
 を見ると春が来ているのを感じます。
を見ると春が来ているのを感じます。今日は雨ですが、濡れた桜もきれいです。
ただ、巷は新型コロナ感染症の影響で
春のうららかさが少ないのは残念です。
特に授乳中のママは普段の薬が使えず
「つらい
 」との声が聞こえてきます。
」との声が聞こえてきます。内服にしても点眼薬にしても添付文書をみると
“授乳を避けること”と記載されています。
授乳を優先すべきか、それとも治療を優先すべきか
悩んでしまいますね。
内服薬として多く使われるものには抗ヒスタミン剤があります。
第2世代の抗ヒスタミン剤は母乳中に移行する量が少ないものもあり、
授乳への影響が少ないといわれています。
内服はしないにしても、点眼薬や点鼻薬を使えるのかと
心配する方もいらっしゃいます。
内服薬と比較すると、点眼薬の使用では、ママの血液中に
吸収される薬の量はごくわずかで問題ないことが多いです。
薬の種類により違いがあるので、
花粉症がひどい場合は、かかりつけの医師に授乳中であること
授乳中でも使用できる薬が欲しいことを相談してみましょう。
花粉症の季節も今までと同じように母乳育児を楽しめるといいですね


2020年03月09日
哺乳瓶嫌いの赤ちゃんを預けたいとき
こんにちは しんしろ助産所です
「今度、結婚式があって子どもを預けたいけど、
哺乳瓶を嫌がって飲まないのでどうしよう・・・」
そんな相談を受けることがあります。
哺乳瓶を嫌がるようになる赤ちゃんは
完全母乳の場合に多くみられますが、
混合栄養でどちらも飲んでいたのに
途中から嫌がるようになることもあります。
ママのおっぱいと哺乳瓶の違いがわかるのは
成長の証でもありますが、赤ちゃんを
預ける方も預かる方も困ってしまいますね
まずは、もしかしたら哺乳瓶で
飲めるかもしれない方法です。
●哺乳瓶の乳首の種類・サイズを変えてみる
乳首の種類やサイズを変えることで
感触や出具合を変えてみる。
●哺乳瓶の乳首を温めてみる
ママのおっぱいが温かいのと同じようにしてみる。
●まどろみ授乳
眠いときや寝起きのまどろんでいるときは
こだわりが強くなく、受け入れてくれやすい。
それをきっかけに飲めるようになることも・・・
●ミルクではなく、搾乳した母乳をあげてみる
飲み慣れたママのおっぱいの方が受け入れやすい。
●おっぱいから哺乳瓶にすり替える
最初におっぱいを吸わせ、途中で
哺乳瓶にすり替えてみる。
●哺乳瓶の乳首をおもちゃとして遊ばせ慣れさせる
どうしても哺乳瓶が飲めない場合、
哺乳瓶を使わずに授乳する方法です。
●スプーンやカップでの授乳
カップ授乳はインターネットで検索すると動画もあるので
参考にするといいですね。
●スパウトやストロー
月齢にもよりますが、スパウトやストローで
飲めるようになることも・・・
その他、いつも通りママのおっぱいを
飲んでもらう方法として
「家の人に赤ちゃんを連れて会場近くで待機してもらい、
連れてきてもらって授乳した」
という人もみえます。
結婚式など、その日のうちの
数時間のことであればなんとかなるものです。
一度にたくさん飲めなくても
少しずつ分けてでも大丈夫です。
落ち込んだり、イライラせず
いろいろな方法を試してみましょう

「今度、結婚式があって子どもを預けたいけど、
哺乳瓶を嫌がって飲まないのでどうしよう・・・」
そんな相談を受けることがあります。
哺乳瓶を嫌がるようになる赤ちゃんは
完全母乳の場合に多くみられますが、
混合栄養でどちらも飲んでいたのに
途中から嫌がるようになることもあります。
ママのおっぱいと哺乳瓶の違いがわかるのは
成長の証でもありますが、赤ちゃんを
預ける方も預かる方も困ってしまいますね

まずは、もしかしたら哺乳瓶で
飲めるかもしれない方法です。
●哺乳瓶の乳首の種類・サイズを変えてみる
乳首の種類やサイズを変えることで
感触や出具合を変えてみる。
●哺乳瓶の乳首を温めてみる
ママのおっぱいが温かいのと同じようにしてみる。
●まどろみ授乳
眠いときや寝起きのまどろんでいるときは
こだわりが強くなく、受け入れてくれやすい。
それをきっかけに飲めるようになることも・・・
●ミルクではなく、搾乳した母乳をあげてみる
飲み慣れたママのおっぱいの方が受け入れやすい。
●おっぱいから哺乳瓶にすり替える
最初におっぱいを吸わせ、途中で
哺乳瓶にすり替えてみる。
●哺乳瓶の乳首をおもちゃとして遊ばせ慣れさせる
哺乳瓶を使わずに授乳する方法です。
●スプーンやカップでの授乳
おちょこや小さめのコップ、スプーン、スポイトなどを
使って少しずつ飲ませる。
流しこむとむせてしまうので注意しましょう。カップ授乳はインターネットで検索すると動画もあるので
参考にするといいですね。
●スパウトやストロー
月齢にもよりますが、スパウトやストローで
飲めるようになることも・・・
飲んでもらう方法として
「家の人に赤ちゃんを連れて会場近くで待機してもらい、
連れてきてもらって授乳した」
という人もみえます。
結婚式など、その日のうちの
数時間のことであればなんとかなるものです。
一度にたくさん飲めなくても
少しずつ分けてでも大丈夫です。
落ち込んだり、イライラせず
いろいろな方法を試してみましょう

2020年02月27日
復職後の授乳
こんにちは しんしろ助産所です
今年は暖冬で桜の花 が咲き始めたところもあるとか…
が咲き始めたところもあるとか…
春はもうすぐですね。
年度の切り替えの時期です。
入園・入学とともに職場復帰されるママさんも見えると思います。
仕事をするにあたり、
ママが真っ先に考えるのは子どもの預け先。
祖父母などの家族にお願いする、保育園に入れるなど
状況は人それぞれですね。
まだ年齢の小さいお子さんのママは、預け先の次に考えるのは
授乳のことが多いのではないでしょうか。
助産所にも、授乳を継続するのか、
またどういうタイミングで断乳するのかと
相談に来られる方もいます。
あるアンケートでは、育児休暇から職場復帰した場合、
「仕事復帰後も授乳を継続したい 」と思っているママは約6割いて、
」と思っているママは約6割いて、
実際に6割強のママが授乳を継続しているとのこと。
その理由としては
①できるだけ母乳をあげたい
②月齢が小さい
③おっぱいが好き
④スキンシップのため
⑤子ども、ママ両方の精神安定のため
などがあげられます。
といっても、おっぱいトラブル、母乳分泌量の減少、搾乳できるのかなど
続けることに対して不安を抱くママも多いです。
また、仕事復帰に合わせて断乳をするママもいます。
フルタイムでの復帰や通勤に時間がかかる、夜間の授乳もある、
体力的につらいなどがその理由。
最終的に復帰後の授乳をどうするのかは、
ママや子ども、家族がその時期を判断するということになります。
いろいろな状況を踏まえたうえで出した答えはベストだと思います。
不安になる必要はありません。
復職後の授乳についてどうするかなど
不安がある方は病院や助産所にご相談ください。

今年は暖冬で桜の花
 が咲き始めたところもあるとか…
が咲き始めたところもあるとか…春はもうすぐですね。
年度の切り替えの時期です。
入園・入学とともに職場復帰されるママさんも見えると思います。
仕事をするにあたり、
ママが真っ先に考えるのは子どもの預け先。
祖父母などの家族にお願いする、保育園に入れるなど
状況は人それぞれですね。
まだ年齢の小さいお子さんのママは、預け先の次に考えるのは
授乳のことが多いのではないでしょうか。
助産所にも、授乳を継続するのか、
またどういうタイミングで断乳するのかと
相談に来られる方もいます。
あるアンケートでは、育児休暇から職場復帰した場合、
「仕事復帰後も授乳を継続したい
 」と思っているママは約6割いて、
」と思っているママは約6割いて、実際に6割強のママが授乳を継続しているとのこと。
その理由としては
①できるだけ母乳をあげたい
②月齢が小さい
③おっぱいが好き
④スキンシップのため
⑤子ども、ママ両方の精神安定のため
などがあげられます。
といっても、おっぱいトラブル、母乳分泌量の減少、搾乳できるのかなど
続けることに対して不安を抱くママも多いです。
また、仕事復帰に合わせて断乳をするママもいます。
フルタイムでの復帰や通勤に時間がかかる、夜間の授乳もある、
体力的につらいなどがその理由。
最終的に復帰後の授乳をどうするのかは、
ママや子ども、家族がその時期を判断するということになります。
いろいろな状況を踏まえたうえで出した答えはベストだと思います。
不安になる必要はありません。
復職後の授乳についてどうするかなど
不安がある方は病院や助産所にご相談ください。
2020年02月18日
授乳中、授乳後のおっぱいの痛み
こんにちは しんしろ助産所です
普段はそんなことないのに
なぜか授乳をすると、
その途中や授乳後にかけて
乳頭やおっぱいが痛くなる・・・
という相談が時々あります。
もうミルクにしてしまいたい
という思いがよぎるほど
痛みを伴う授乳は苦痛を感じるものです。
授乳中、授乳後に乳頭や乳房の痛みを
引き起こす原因で考えられるのは
白斑や乳口炎、レイノー現象、カンジダによる感染
などですが、原因が特定できない場合もあります。
〈白斑、乳口炎〉
乳頭の先端にニキビのような白い斑点ができ、
授乳時に痛みを伴うことが多いものです。
乳口に保湿剤を塗ってラップ療法をしたり、
口内炎の薬が効くこともあります。
乳口が塞がって、おっぱいが詰まってしまう
こともあるので、含ませる方向を変えて授乳したり、
搾乳をしてもとれないときは、ご相談ください。
〈レイノー現象〉
授乳後に乳頭が真っ白に虚血した状態になり、
乳頭や乳房に刺すような痛みを感じます。
この時に乳頭や乳房を温めると和らぐようです。
〈カンジダによる感染〉
カンジダによる感染があると、
授乳中から刺すような痛みがだんだんと
強くなって来ることがあります。
乳頭・乳輪部のかゆみや赤み、赤ちゃんの口の中が
白っぽくなるなどの症状が多く見られますが、
分かりにくいこともあります。
疑われる場合は医療機関で診てもらいましょう。
痛みから解放され、また幸せな授乳タイムが
過ごせるよう、まずは、ひとりで悩まず、

普段はそんなことないのに
なぜか授乳をすると、
その途中や授乳後にかけて
乳頭やおっぱいが痛くなる・・・

という相談が時々あります。
もうミルクにしてしまいたい
という思いがよぎるほど
痛みを伴う授乳は苦痛を感じるものです。
授乳中、授乳後に乳頭や乳房の痛みを
引き起こす原因で考えられるのは
白斑や乳口炎、レイノー現象、カンジダによる感染
などですが、原因が特定できない場合もあります。
〈白斑、乳口炎〉
乳頭の先端にニキビのような白い斑点ができ、
授乳時に痛みを伴うことが多いものです。
乳口に保湿剤を塗ってラップ療法をしたり、
口内炎の薬が効くこともあります。
乳口が塞がって、おっぱいが詰まってしまう
こともあるので、含ませる方向を変えて授乳したり、
搾乳をしてもとれないときは、ご相談ください。
〈レイノー現象〉
授乳後に乳頭が真っ白に虚血した状態になり、
乳頭や乳房に刺すような痛みを感じます。
この時に乳頭や乳房を温めると和らぐようです。
〈カンジダによる感染〉
カンジダによる感染があると、
授乳中から刺すような痛みがだんだんと
強くなって来ることがあります。
乳頭・乳輪部のかゆみや赤み、赤ちゃんの口の中が
白っぽくなるなどの症状が多く見られますが、
分かりにくいこともあります。
疑われる場合は医療機関で診てもらいましょう。
痛みから解放され、また幸せな授乳タイムが
過ごせるよう、まずは、ひとりで悩まず、
ご相談くださいね

2020年02月17日
夜間授乳と虫歯
こんにちは しんしろ助産所です
「虫歯になるので、1歳を過ぎたら夜間の授乳をやめた方がいいですか」と
相談を受けました。
虫歯予防と夜間の授乳、悩ましい問題です。
ある先生は、
「確かに夜間の授乳は歯磨きまでできないので虫歯のリスクにはなりえるが
そうでなかった場合より、虫歯になるリスクは半分である 」
」
との記述もあり、母乳が虫歯のリスクを下げている可能性が
あることもいわれています。
母乳に含まれる乳糖をミュータンス菌(虫歯の原因とされる細菌)と
混合して調べた結果、乳糖だけでは虫歯の原因となる酸がほとんど産生されず、
 と言われています。
と言われています。
母乳育児には多くのメリットがあり、
・中耳炎や気道感染などの感染症にかかりにくくなる
・小児の肥満のリスクを下げる
など、母乳推進の根拠となっています。
以上のことをまとめると
・1歳過ぎてからの夜間の授乳は虫歯のリスクを高める可能性があるが
それは不十分な口腔ケアで食べかすが残っていることが原因かもしれない
・母乳育児のメリットは多くあるので、できれば続けた方がいい
つまり虫歯対策として大切なのは夜間の授乳をやめることではなく、
口腔内のケアをしっかり行うこと です。
です。


「虫歯になるので、1歳を過ぎたら夜間の授乳をやめた方がいいですか」と
相談を受けました。
ある先生は、
「確かに夜間の授乳は歯磨きまでできないので虫歯のリスクにはなりえるが
それを理由に夜間授乳をやめるというのは賛成できない 」と
」と
 」と
」とお話しされていました。
母乳栄養と虫歯の関係について研究された
多くの論文をまとめ検討されたものでは、
「生後12か月を超えて母乳育児を続けた場合、
12か月未満で終えた場合と比べ、虫歯のリスクが1.99倍 」 だそう。
」 だそう。
 」 だそう。
」 だそう。しかし、同じ文中に
「ただし生後12か月までの間に限ると、母乳育児期間が長かった場合は、そうでなかった場合より、虫歯になるリスクは半分である
 」
」との記述もあり、母乳が虫歯のリスクを下げている可能性が
あることもいわれています。
何が正しいのかわからなくなりますね。
混合して調べた結果、乳糖だけでは虫歯の原因となる酸がほとんど産生されず、
乳糖が他の糖質と混ざる場合に酸が産生されたとの報告があります。
つまり、授乳そのものではなく、食べ物などの残りかすなどで
口内にいろいろな糖質が混じりあい虫歯につながるのでは… と言われています。
と言われています。母乳育児には多くのメリットがあり、
・中耳炎や気道感染などの感染症にかかりにくくなる
・小児の肥満のリスクを下げる
など、母乳推進の根拠となっています。
・1歳過ぎてからの夜間の授乳は虫歯のリスクを高める可能性があるが
それは不十分な口腔ケアで食べかすが残っていることが原因かもしれない
・母乳育児のメリットは多くあるので、できれば続けた方がいい
ということ
口腔内のケアをしっかり行うこと
 です。
です。乳歯が生え始めたら、口腔ケアをしっかりし、
離乳食を与えた後はしっかり歯磨きしていきましょう。

2020年01月30日
授乳ストラップ
こんにちは しんしろ助産所です
赤ちゃんがうまれると、毎日頻回の授乳が必須
そのため、母乳のママは、授乳しやすい服を着ることが多くなりますが、
授乳服をそろえるのも大変です。
デザインもそうですが、授乳中しか着れないと考えると
なんかもったいない気がします。
授乳ストラップとは、授乳時に洋服が下がってこないようにする
ストラップのことを言います。
・前あきの服が少ない
・授乳専用の服がない
・授乳中に服が赤ちゃんの顔にかかってしまうのが気になる
などの方はぜひ使ってみてください。
市販のものもありますが、ゴムを使って簡単に作れます。
ヘアゴム(長いもの)をネックレス風に結び、
それを首にかけ、服の中から通し、下から出たゴムを首にかけるだけです。
そうすると赤ちゃんの顔にママの服がかかることもなく、
服を手で支える必要もありません。
ヘアゴムだとかさばりませんし、使わないときは首にかけたまま
服の中に入れておくと気になりません。
また、お裁縫が得意な方はシュシュのように全体を布で覆ったり、
革ひもや麻ひもに大きめのボタンなどをつけて作ってもいいでしょう。
手軽に作れて、ママも快適ですよ

赤ちゃんがうまれると、毎日頻回の授乳が必須

そのため、母乳のママは、授乳しやすい服を着ることが多くなりますが、
授乳服をそろえるのも大変です。
デザインもそうですが、授乳中しか着れないと考えると
なんかもったいない気がします。
そんな時には授乳ストラップを使用するのがおすすめ

授乳ストラップとは、授乳時に洋服が下がってこないようにする
ストラップのことを言います。
・前あきの服が少ない
・授乳専用の服がない
・授乳中に服が赤ちゃんの顔にかかってしまうのが気になる
などの方はぜひ使ってみてください。
市販のものもありますが、ゴムを使って簡単に作れます。
ヘアゴム(長いもの)をネックレス風に結び、
それを首にかけ、服の中から通し、下から出たゴムを首にかけるだけです。
そうすると赤ちゃんの顔にママの服がかかることもなく、
服を手で支える必要もありません。
ヘアゴムだとかさばりませんし、使わないときは首にかけたまま
服の中に入れておくと気になりません。
また、お裁縫が得意な方はシュシュのように全体を布で覆ったり、
革ひもや麻ひもに大きめのボタンなどをつけて作ってもいいでしょう。
手軽に作れて、ママも快適ですよ

2019年12月17日
乳腺炎
こんにちは しんしろ助産所です
授乳期に起こりやすいトラブルの一つに
乳腺炎があります。
乳腺炎には大きく分けて2種類あります。
一つは「うっ滞性乳腺炎」、
もう一つは「感染性乳腺炎」です。
「うっ滞性乳腺炎」は乳汁が何らかの原因で
滞ってしまった状態をいいます。
お母さん方は自分の食べたもの、
例えばケーキやチョコレート、揚げ物などにより
詰まってしまったと自分を責めがちですが
関連性の有無は はっきりしていません。
むしろ、来所された母子の様子から
●授乳間隔があいてしまった、
●外出先で授乳・搾乳ができなかった
●赤ちゃんが鼻づまりでうまく吸えない
●白斑ができており、そこから乳汁が出ない
などが主な原因のように感じます。
「感染性乳腺炎」は授乳の際、
赤ちゃんの口を介して
細菌感染をすることで発症します。
赤ちゃんに噛まれるなどで 乳頭にできた傷口から
感染を起こすことが多いようです。
白斑や乳頭にできた水疱を 無理に破ったり
針で突くなどした場合も感染のおそれがあります。
症状としては、乳房の腫脹、疼痛、熱感、硬結、
発赤に加え38℃以上の高熱の持続を伴います。
感染性乳腺炎が強く疑われる場合は
搾乳だけでなく、医療機関への受診が必要です。
赤ちゃんが風邪をひきやすいこの時期、
うまく吸えないことによる乳頭トラブルが
起こりやすくなります。
1回の授乳量が減った場合は 授乳回数を増やす、
スッキリしない場合は搾乳をする、
浅飲みを避けるなど
予防と対策をおこないましょう。
そして改善しない場合は早めにご相談くださいね

授乳期に起こりやすいトラブルの一つに
乳腺炎があります。
乳腺炎には大きく分けて2種類あります。
一つは「うっ滞性乳腺炎」、
もう一つは「感染性乳腺炎」です。
「うっ滞性乳腺炎」は乳汁が何らかの原因で
滞ってしまった状態をいいます。
お母さん方は自分の食べたもの、
例えばケーキやチョコレート、揚げ物などにより
詰まってしまったと自分を責めがちですが
関連性の有無は はっきりしていません。
むしろ、来所された母子の様子から
●授乳間隔があいてしまった、
●外出先で授乳・搾乳ができなかった
●赤ちゃんが鼻づまりでうまく吸えない
●白斑ができており、そこから乳汁が出ない
などが主な原因のように感じます。
「感染性乳腺炎」は授乳の際、
赤ちゃんの口を介して
細菌感染をすることで発症します。
赤ちゃんに噛まれるなどで 乳頭にできた傷口から
感染を起こすことが多いようです。
白斑や乳頭にできた水疱を 無理に破ったり
針で突くなどした場合も感染のおそれがあります。
症状としては、乳房の腫脹、疼痛、熱感、硬結、
発赤に加え38℃以上の高熱の持続を伴います。
感染性乳腺炎が強く疑われる場合は
搾乳だけでなく、医療機関への受診が必要です。
赤ちゃんが風邪をひきやすいこの時期、
うまく吸えないことによる乳頭トラブルが
起こりやすくなります。
1回の授乳量が減った場合は 授乳回数を増やす、
スッキリしない場合は搾乳をする、
浅飲みを避けるなど
予防と対策をおこないましょう。
そして改善しない場合は早めにご相談くださいね

2019年10月28日
差し乳・溜まり乳
こんにちは しんしろ助産所です
「差し乳」「溜まり乳」という言葉を
お母さん方からよく聞きます。
差し乳は
「普段は空っぽだが、赤ちゃんが飲み始めると
製造工場が稼働して、新鮮な乳汁が出てくる」
溜まり乳は
「母乳の分泌がよく、授乳間隔があくと
張って痛くなったり、漏れてきたりする状態」
といったイメージでしょうか?
でも「差し乳」も「溜まり乳」も
正式な医学用語ではありません。
赤ちゃんにおっぱいを吸われた時のツーンとする
一般に「差し乳」と呼ばれる現象は
新鮮な乳汁の生産スイッチと信じられていました。
でも、これは射乳ホルモンである「オキシトシン」により
乳腺組織の筋肉が収縮した状態であり、
溜まっていた母乳が押し出されている状態なのです。
一方で一般に「溜まり乳」と呼ばれる状況は、
母乳過多でうっ滞性乳腺炎などの
トラブルが起こりやすい状況といえます。
実はどのおっぱいも24時間生産され続け、
溜められている点では「溜まり乳」と言えます。
そして、作られる母乳の量は、
乳房に溜まっている母乳量によって変わります。
乳汁には「乳汁分泌抑制因子」という物質が
含まれているため
乳汁が飲み取られれば早いスピードで生産され、
溜まっていればゆっくりと生産されます。
おっぱいの大きさによっても
溜められる量は違いますが
おっぱいが張っていなくても、授乳の直後でも
完全に空になることはないので
分泌の少ない人ほど飲ませるようにしましょう

「差し乳」「溜まり乳」という言葉を
お母さん方からよく聞きます。
差し乳は
「普段は空っぽだが、赤ちゃんが飲み始めると
製造工場が稼働して、新鮮な乳汁が出てくる」
溜まり乳は
「母乳の分泌がよく、授乳間隔があくと
張って痛くなったり、漏れてきたりする状態」
といったイメージでしょうか?
でも「差し乳」も「溜まり乳」も
正式な医学用語ではありません。
赤ちゃんにおっぱいを吸われた時のツーンとする
一般に「差し乳」と呼ばれる現象は
新鮮な乳汁の生産スイッチと信じられていました。
でも、これは射乳ホルモンである「オキシトシン」により
乳腺組織の筋肉が収縮した状態であり、
溜まっていた母乳が押し出されている状態なのです。
一方で一般に「溜まり乳」と呼ばれる状況は、
母乳過多でうっ滞性乳腺炎などの
トラブルが起こりやすい状況といえます。
実はどのおっぱいも24時間生産され続け、
溜められている点では「溜まり乳」と言えます。
そして、作られる母乳の量は、
乳房に溜まっている母乳量によって変わります。
乳汁には「乳汁分泌抑制因子」という物質が
含まれているため
乳汁が飲み取られれば早いスピードで生産され、
溜まっていればゆっくりと生産されます。
おっぱいの大きさによっても
溜められる量は違いますが
おっぱいが張っていなくても、授乳の直後でも
完全に空になることはないので
分泌の少ない人ほど飲ませるようにしましょう