2017年06月30日
母乳通信 第26号「哺乳ストライキ」を発行しました

しんしろ助産所では
母乳で育てたいママ・プレママを応援するため、
母乳育児に関する考え方や手技をまとめた
母乳通信を発行しています。
今回は
今までに何度か相談のあった「哺乳ストライキ」
をまとめました。
赤ちゃんが突然、哺乳しようとするとのけぞって嫌がったり、
お腹がすいているのに顔をそむけられたりする「哺乳ストライキ」
実際、困ってしまいますね。
そのきっかけはいろいろあって、
おっぱいを噛まれて大きな声を出した
風邪を引いて鼻が詰まりが苦しそうだった
口の中に白いできものができた ・・・など。
どうして飲んでくれないのかな?
もう卒乳?
おっぱいが張って痛くてたまらない

おっぱいが飲めない間はどうしたらいいの?
また飲んでくれるようになるかしら・・・
ママが途方にくれないよう
哺乳ストライキの原因や対処法について
まとめました。
これまでのバックナンバーと併せて
新城市のホームページ、新城市子育て情報ナビ「咲くら」
からもご覧いただけます。
ぜひ、ご活用ください

クリックすると画像が拡大します

2017年06月29日
かわいいお客さま
こんにちは しんしろ助産所です
今日は助産所にきてくれたかわいいお客様たちを
ご紹介します。
もうすぐ2ヶ月になるAちゃん
始め起きていたのが、抱っこさせてもらっているうちに
スヤスヤ![]()
楽しい夢みてるのかな…
ニコッと微笑んでくれました。
こんな表情に出会うと気持ちがほっこりします
またきてね
1才6ヶ月のRちゃん
ママを待っている間、おばあちゃんと絵本やDVDを
みて待っていてくれました。
アンパンマンが大好き なんだって。
なんだって。
大好きなアンパンマンの絵本やDVDがあってよかったね。
後で児童館の遊具でいっぱい遊べたかな
1ヶ月のMくん、抱っこが大好き
抱っこしてると機嫌よく寝てくれるそう。
今は実家にいるのだけれど、パパのジィジとバァバも
早く戻ってこないかなぁ…って心待ちにしてくれてるそうです。
もう少ししたら帰るからね
とても活発なAくん、11ヶ月
色々なものに興味津々~ 終始動き回ってます。
終始動き回ってます。
生後すぐのころから知ってるけれど、
ますますママに似てきたね
また来てね。待ってまぁす
2017年06月28日
手足口病

手足口病は、プール熱、ヘルパンギーナと並び、
夏に子どもがかかりやすい夏風邪の一つ。
厚生労働省の感染症発生動向調査では、
手足口病の2017年の報告数は増加
 が続いており、
が続いており、これから流行期を迎える時期と予想されるため、注意が必要と呼びかけています。
原因はコクサッキーウイルスやエンテロウイルスの感染で、
潜伏期間は1~3週間

保育園・学校等、子どもが多く集まる場所で集団発生することも…

手のひらや足、口の中に赤い斑点や水疱ができ、発熱を伴うこともあります。
特に口の中の水疱が破れると口内炎様の痛みがあり、
食事や飲み物を受けつけなくなることがあります。
残念ながら手足口病には特効薬はなく、症状に応じた対症療法になります。
時に、髄膜炎や脳炎を併発するおそれもあるため、手足口病が疑わしいときは、
自己判断せず、医師の診断
 を受けましょう。
を受けましょう。発熱に伴う倦怠感や食欲低下に加え、口内の痛みや不快感が強いため、
食事やミルク等を嫌がることもあります。
そうなると乳幼児は脱水が心配
 暑い時期なので水分補給は必須です!!
暑い時期なので水分補給は必須です!!お茶や白湯など飲めそうなものを積極的に飲ませましょう。
ミルクは飲めなくても、おっぱいなら飲める子もいます。
口内炎の痛みを増長するような酸味のあるもの、熱いもの、塩分が強いものなどは避け、
消化が良くのど越しの良いものを少しずつあげるようにしましょう。
アイスクリームや豆腐、プリンやゼリーなどが食べやすいようです。
手足口病のウイルスは、10種類以上もあり、
一度罹ってもウイルスが違えば、また罹ることもあります。
常日頃から、手洗いやうがいを励行し、予防に努めましょう。

2017年06月27日
授乳と乳がん

先日の小林麻央さんの訃報、
本当に驚きました。
いつかこの日が来るかもしれない…と覚悟しつつも、
いつも明るい笑顔と 前向きな言葉で綴られるブログを見ると
「もしかしたら また元気な姿を見せてくれるかも…」
という願いと希望を抱いていました。
本当に無念でなりません。
麻央さんの病名公表やブログによって
乳がんに対する意識は 確実に上がったと感じています。
助産所でも 授乳期や断乳・卒乳の相談が
一気に増えました。
相談の多くは大きく分けて以下の3点です。
●しこりに気づいたが、心配はない?
●授乳中でも乳がん検診はできるの?
●断乳・卒乳の際、きれいに搾り切らないと乳がんになる?
(以前のブログも併せてご覧ください ① ②)
●しこりに気づいたが、心配はない?
授乳期には乳腺が詰まり、しこりになることがあります。
でも、開通すればしこりは小さくなったり 消失したりします。
「なかなか小さくならない」、「少しずつ大きくなった」
という場合は 医療機関への受診をお勧めします。
●授乳中でも乳がん検診はできるの?
授乳期でも検診を受けることが出来ます。
授乳期はマンモグラフィーが適さないことが多いため、
集団検診は避けた方が無難ですね。
医療機関に受診する際は
事前に授乳期であることを伝えておきましょう。
●断乳・卒乳の際、きれいに搾り切らないと乳がんになる?
よく耳にする噂なので、本当に心配になってしまいますね。
結論からいうと、そんなことはありません。
残った乳汁ががん化する訳ではないので 心配ありません。
ただ、乳汁が残っていてもある程度は吸収しますが
しこりとして残ってしまうこともあるため
すっきり搾った方が安心ですね。
一時の関心ごととせずに、
定期的に自己検診をしたり 乳がん検診をうけるなど、
伝えてくれた大切なメッセージを
真摯に受け止めていきたいですね。
2017年06月26日
離乳食が大変と思っていませんか?

今朝、出勤すると
隣の児童館に七夕の笹飾りが飾られていました

もうそんな季節なんですね。
みんなの願い事がかなうといいな


さて、生後5~6ヶ月頃になると
それまで母乳やミルクで育ってきた赤ちゃんも
離乳食を始める時期がやってきます。
赤ちゃんのために頑張りたいけど、
毎日の家事・育児に加えて
手間のかかる離乳食作り。
誰でも一度は「面倒くさいなあ・・・
 」
」と思うことがあるかもしれません。
そうは言っても始めないわけにはいけません。
途中で投げ出すわけにもきません。
毎日無理なく続けるには
できるだけ時間や手間をかけず、
効率的に行うのがコツです。
1.フリージング
毎回、少ない量の離乳食を
その都度作るのは大変なことです。
時間のある時に、おかゆや野菜の下ごしらえなど、
まとめて作って冷凍しておくと
作る時に時間短縮ができて楽です。
2.大人の料理から取り分ける
大人用の料理を作る時、
赤ちゃんが食べられる食材があれば
味付け前に具材を取り分けると楽です。
3.便利な調理器具を活用
すり鉢、裏ごし器、おろし器の他、
シリコンスチーマーやブレンダー、調理バサミなど、
離乳食作りに便利なグッズを活用されるのも一法です。
4.市販のベビーフードを活用
そのまま食べさせるもよし、
味付けやアレンジに応用することもできます。
5.おかゆ作り
離乳食の基本となる主食のおかゆ。
耐熱容器を使って、炊飯器で
大人のご飯と一緒に炊く方法も便利です。
初期のおかゆには米粉を使ったら楽だった

というママも見えました。
はじめて離乳食をつくるママは
ちゃんと作らないと・・・と 自然に力が入りやすいもの。
時短調理や既製品も上手く使って
楽しい離乳食タイムを過ごしましょう

2017年06月23日
妊娠と歯周病予防
こんにちは しんしろ助産所です
歯周病があると歯茎から出血したり、腫れたりといった
口腔内だけの影響にに留まらず、血管を通して炎症物質が
全身に影響する(脳梗塞や心筋梗塞、糖尿病などといった
疾患を引き起こす)ことが分かっています。
妊娠は病気ではありませんが、やはり歯周病があると
早産や低体重児出産のリスクが高まります。
低体重児ではなんと7.5倍!
これは喫煙や高齢出産、アルコールをはるかに上回ります。
歯周病と低体重児早産
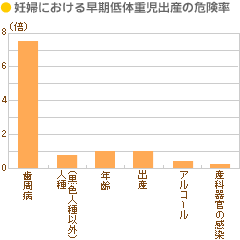
歯周病は治療や予防ができます。
つわりで食生活が不規則になったり、歯磨きが上手くできない時期もありますが
そのままにしておくと進行して後になって後悔しないとも限りません。
母子手帳には歯科健診の助成券がついています。
働いていると、なかなか自分の歯に治療やケアにまで時間が取りにくい方も
みえるでしょうが、なるべく安定期(妊娠16週~妊娠27週)には健診票を上手く使って
歯科衛生に気をつけましょう。
2017年06月22日
梅雨の時期の食中毒の予防
こんにちは しんしろ助産所です
昨日は警報が出る程の土砂降り、河川の水位も高くて心配しました。
今日は雨もやみましたが、湿度は高め
この時期特有のジメジメ感があります。
梅雨をはさんだ5月~9月は、食中毒が多く発生する時期
テレビで集団食中毒などのニュースが流れますが、
お肉や魚を生で食べたりしなければ大丈夫と思っている方もいるかもしれません。
しかし、それだけが原因ではありません。
食中毒の原因は細菌によるものとウイルスによるもの。
梅雨時の食中毒の多くは細菌によるものが多数を占めています。
そこで、細菌性の食中毒予防についてまとめました。
細菌性の食中毒は、肉や魚、たまごなど食品の中で繁殖した菌が、
食品と共に体内に取り込まれることでさらに増殖し、
腹痛や下痢、嘔吐、発熱等の症状があらわれます。

【予防の3原則】
 つけない
つけない
調理前に手指を清潔にし、調理物品(包丁やまな板など)はしっかり流水で洗い流す。
食器は清潔な乾燥した布巾を使う。食器洗浄乾燥器も有効
 増やさない
増やさない
肉・魚・野菜等生の食品は冷蔵庫で管理する。生ものは早めに調理して食べること。
調理後長く放置すると、再び菌が増殖する
冷蔵庫の開閉や食品の入れ過ぎに気を付け、温度管理をしっかりとする
 やっつける
やっつける
生ものは控え、火をしっかり通して食べる。肉・魚。卵などはしっかりと中まで火を通す。
75℃で1分以上加熱すると細菌の多くは死滅する。
食中毒を起こす主な細菌である、サルモネラ菌、ブドウ球菌、腸炎ビブリオ等は
65℃以上の加熱で死滅するといわれている。
赤ちゃんのいる家庭では、夏場の哺乳瓶に要注意!!
哺乳瓶を使用後、洗浄するときは、乳首や瓶の接続部分をしっかり洗い、汚れを落とすこと
使い終わったら、きちんと洗い、消毒して保管するのがベストです。
食中毒が心配なこの時期ですが、正しい知識や予防法を知ることで
ある程度は防ぐことができます。
食品の取り扱いに十分に注意し、家族みんなが安全安心に食せるよう心がけましょう
2017年06月21日
離乳食教室に参加してきました

助産所で働いていると、よく離乳食の相談を受けます。
正直 学生時代に離乳食について勉強するかというと
(最近のカリキュラムは分かりませんが)
そのような授業はなかったため
自分の子育て経験や、厚労省の離乳食ガイドライン、
本で得た知識から おこたえしています。
「もう少し具体的に勉強したいな・・・」 という気持ちと
わが家の子どもたちは 離乳食を嫌がり、
食べなかった という苦い経験から
先日 離乳食教室に参加してきました。
●離乳食完了は1歳半?
消化酵素や腸内環境が整うのは3~4歳
肝機能や腎機能が整うのは8歳
と言われているため
おっぱいを卒業したからと言って
一気に進めるのは 赤ちゃんにはかえって負担。
●食べ過ぎる赤ちゃんは・・・
食欲旺盛な赤ちゃんの場合は
内臓に負担をかけないために、
タンパク質と脂肪分を控え
それ以外のもの(野菜や炭水化物)で
食欲を満たしてあげるのが良い。
●五感の中で食べ物を一番感じる感覚は・・・
もちろん「味覚!」と思ったのですが
味覚から得る情報は1~5%とか。
なんと「視覚」から80%を感じるのだそう。
何より、ママがリラックスして
美味しそうに 笑顔で食卓を囲むことが大切。
●赤ちゃんが欲しがる量が今の適量
赤ちゃんが食事を嫌がったり
食が細いくて不安になるママも大勢います。
でも、「まぁ、いいか」「これが今の適量」 と
割り切りましょう。
実際の調理では
●トマトは湯剥きをし、種を取る
●オクラも板摺をし、種を取る
●大根やかぶは皮を厚めに切る
●魚は(水分を蒸発させるとパサつくため)蒸し焼きに
下処理をしたものと していないもので食べ比べましたが
舌や上あごだけで食べようと思ったときに
皮や種は思った以上に食感がわるいこと、
根菜類は厚めに皮を剥くことで
繊維が残りにくく、舌触りがいいことを実感しました。
●ジャガイモ、麩、オクラを使ったとろみ付け
●昆布だしの活用
とろみのバリエーションを変えると
風味や食感・栄養にも変化をつけられること
等を舌で感じとることができ美味しくいただけました。
実際、頑張って作っても食べてくれないこともあるし
好き嫌いが激しい赤ちゃんもいます。
食べないものは 食べないし、
食べない子は 食べないのかもしれませんね。
でも、大事なのは
楽しい雰囲気とママの笑顔、
そして「赤ちゃんが欲しがる量が今の適量」
「まぁ、いいか」 と、肩の力をぬいた余裕なのかもしれません。
2017年06月20日
妊婦さんの足の付け根の痛み

妊娠してから
「足の付け根の辺りが痛い
 」
」と心配される妊婦さんは比較的多くみえます。
“つっぱるような痛み”と
表現されることが多いこの痛みの原因は、
まさしく子宮を支える靭帯のつっぱり!
子宮はたくさんの靭帯で支えられています。
その中のひとつに円靭帯があります。
妊娠していない時の円靭帯は数センチ。
妊娠して子宮が大きくなるとともに
円靭帯も引き伸ばされ、
最終的には30センチ程にもなるそう

そのため、妊娠初期の円靭帯が伸び始める時期や
妊娠15~25週頃の子宮がぐんぐん大きくなる頃に
痛みが出やすいといわれます。
一般的には、その後症状は治まる傾向にありますが、
もちろん個人差があるのでその限りではありません。
円靭帯のつっぱりによる痛みは
足の付け根以外にも下腹部や恥骨に
感じる人もいます。
切迫症状である場合もあるので、
靭帯の痛みだと決めつけず、
かかりつけ医に相談するようにしましょう。
切迫症状でないことが分かれば、まずはひと安心。
痛みを軽減する方法を試してみてくださいね。
●ヨガやストレッチで靭帯を柔軟にする
●急な動作を避け、ゆっくり動く
●痛みを感じるほうを下にして休む
●骨盤ベルトの着用 など
妊娠中は何かと体調の変化があり、心配になるもの。
お腹が大きくなるのは、
赤ちゃんがすくすく成長している証拠でもあります。
原因や対策を知って、安心してマタニティライフを
過ごせるといいですね

2017年06月19日
しつけで子どもを怖がらせるのは逆効果
こんにちは しんしろ助産所です
小さなお子さんは鬼やおばけを怖がるものですね。
家の子ども叱ったりしたときも、“鬼が連れに来るよ!”とか“お化けがでるよ!”
は効果覿面でした。
なかなか寝ない時も、早く寝ないと“お化けがでるよ!”とか、
“鬼がのぞきに来るよ!”といっていたのですが、いつも自分の方が
先に寝ちゃっていたように思います。
成長した子どもと話をしていて
“お母さんがお化けや鬼がのぞきに来るって脅かすから怖くて寝れなかった ”
”
というのを聞いて、当時は上手くいったとばかり思っていたのですが、
怖がらせていたことに気付きました。
昔話の本で“蜘蛛の糸”や“耳なし芳一”なんかも読んでいたので
よけいに怖がったのかも知れませんが、私に余裕がなかったのですね。
当時はそんな子どもの気持ちを感じることもできませんでした。
こうした怖がらせていうことをきかせようとするのはどうなのでしょうか。
調べてみると賛否両論ありました。
◆賛成意見
・ことばでいっても分からない時期に、“怖い存在”は必要
・成長すれば鬼やお化けがいないことはわかるので心配ない
・嘘も方便
◆反対意見
・怖くていうことをきいているだけで、解決にならない
・夜泣きにつながることもある
・嘘はよくない
その時にはそれが一番だと思ってやっていたのですが
子どもの気持ちにたつとそれもそうだなぁ…と思うことしきり。
叱る場合も、脅すだけではなぜしてはいけないのか、なぜそうするのか
のかを教えなければ行動は変わりません。
寝かす場合も気持ちよく眠りにつけるようなかかわりをしたいもの。
他にも子どもにいうことをきかせようとして
“もう〇〇には連れて行かないよ!” “おやつないから!” “知らないからね!”
などというのも、子どもを力で抑えようとしているのかも知れません。
ただ、怖いからいうことをきくというのは長い目でみればほんの一時期。
子どもにかけることばが脅しや怖がらせてはいないか一度振り返ってみませんか。
2017年06月16日
妊娠中の車の運転

妊娠すると車の運転を控えた方がいいといわれますがどうしていますか。
買い物や仕事、上の子の習い事の送迎、妊婦健診等、
車がなくては生活できない
 という妊婦さんはいらっしゃると思います。
という妊婦さんはいらっしゃると思います。私自身、妊娠中、普通に運転していましたし、今も
 がない生活は考えらません。
がない生活は考えらません。そこで妊娠中の車の運転についてまとめてみました。
妊娠中に ”車の運転はしてはいけない” わけではありませんが
運転することで、いくつかのリスクが伴います

【運転によるリスク】
・注意力が散漫になる
妊娠中は、女性ホルモンの急激な変化により眠気を感じることが多くあります。
眠気が強いと判断力が低下し、注意力も散漫します。
・身体への負担
一定の時間、同じ姿勢でい続けることは、妊婦の腰痛などの原因になることがあります。
運転している緊張で血圧や心拍数が上昇したり、おなかが張ることも

・妊娠末期には、出産徴候が突然現れる可能性がある
臨月に入れば、いつ出産徴候が出てもおかしくありません。
運転中、急に破水したりする場合等に驚いて、通常の運転ができなくなる可能性があります。
等々、色々あげられますが、運転せざるを得ない場合もあります。
その場合は以下の点に注意しましょう
・おなかの張りや異変を感じた場合は、安全な場所に停めて様子をみること
・眠気を感じる場合には、運転をしない、もしくは休息を取ってからにする
・長時間の運転は避ける。やむを得ず長時間運転しなくてはならない場合は、
必ず1時間に1回10分~15分の休憩を取り、身体を動かす
・シートベルトはおなかの圧迫を避け着用することが望ましい
マタニティシートベルトの活用も検討
・可能なら家族などに同乗、もしくは運転してもらう
・母子手帳や保険証はかならず携帯する
・出産徴候が現れた場合は、かかりつけの病院に連絡し、指示を仰ぐ 等
私自身も妊娠中に3時間ほど同じ姿勢で運転していたら、
おなかの張りを感じ、出血したこともありました。
また妊娠中に事故にあい、ハンドルでおなかを強打し、
赤ちゃんがなくなってしまったケースに関わったこともあります。
先日起きた、新城PA近くの高速道路事故のように
想定外の事故が起きないとも限りません。
車に乗らなければ乗らないに越したことはありませんが、
なかなかそうはいきません。
安全運転に心がけるとともに、適宜、家族や周囲の人を頼ったりなど、
無理はしないようにしてくださいね


2017年06月15日
ドライテクニック

「ドライテクニック」ってご存知ですか?
生まれたばかりの赤ちゃんの体には
羊水や血液、胎脂などが付着しています。
日本では従来、赤ちゃんが生まれたら
すぐに沐浴をして体をきれいにする
“産湯” が一般的でした。
現在では、すぐに沐浴はせず、
温かいタオルなどで汚れを拭きとり、
数日経ってから沐浴を開始する方法が増えています。
これを「ドライテクニック」といいます。
沐浴をした方が汚れもきれいに落とせるのでは・・・
と思われるかもしれませんが、
ドライテクニックにはこんなメリットがあります。
●胎脂を残すことで保温・保湿効果がある
生まれたばかりの赤ちゃんの体に
白いクリーム状のようなものが
ついていることがあります。
これが胎脂。
天然の保湿クリームとも呼ばれ、
生まれたばかりの赤ちゃんの肌を保護し、
保温や保湿効果があります。
また、胎脂のにおいは赤ちゃんを安心させる
とも言われています。
●体温低下を防ぐ
体温調節の未熟な赤ちゃん。
沐浴により水分が蒸発する際の
体温の低下を防ぎます。
●沐浴による体力の消耗を防ぐ
●生理的体重減少の割合が少ない
沐浴によるエネルギー消費が減り、
体重減少の割合が少なくなると言われています。
生まれてすぐ対面した赤ちゃんに
胎脂が残っていても
何だか汚れが落ちてないなあ・・・

と思わず、ドライテクニックのメリットを
思い出してくださいね

話は変わって・・・
オープンシステム利用者さんの
お子さんから素敵なお手紙をいただきました
立ち会ったお産の様子が
上手に描かれていてびっくり
よく覚えているんだね
お手紙うれしかったよ。ありがとう

2017年06月14日
甘え上手・泣き上手

子どもが 「甘え上手」 に、
親が 「甘えさせ上手」 になるのは
大切なことです。
甘え上手とは わがままを言うことではなくて
気持ちを素直にさらけ出せることをいい、
お母さんに抱きついて 泣くのもその一つ。
そして 甘えさせ上手とは、
そんな子どもの気持ちをを「よしよし」と
おおらかに受け止めてあげることを言います。
大好きなお母さんに抱っこしてもらいながら、
泣き言を聞いてもらえたらうれしいですね。
「甘え上手」=「泣き上手」 と言えるかもしれません。
以前は 「泣いてはだめ」 「泣く子はヘボい(情けない)」
と言われ、我慢するのがよい子だとされていました。
今でも子どもが泣けば 「泣き止ませるのが親の責任」、
公共機関で赤ちゃんが泣いていると 「うるさい!」 と
心無い言葉を浴びせられることもあります。
子どもを 「泣かせないように」 と
ビクビクしてしまうお母さんもみえるかもしれませんね。
そして 「泣いてはダメ」 と育てられてきた親は
無意識のうちに 「泣かせない子育て」 をするそうです。
そのうち 子どもも 「泣くのはいけないこと」
と思うようになり、泣きたいけれど我慢するようになります。
でも泣くことは自分の心の傷を癒し、
修復している真っ最中。
泣くことを我慢していては
悲しさも悔しさも いつまでも消化できません。
上手に泣いて 負の感情をまるごとお母さんに
受けとめてもらうことで
「自己肯定感が高くなる」 と言われています。
弱音を吐く自分さえも
お母さんは受けとめてくれる と感じることで、
自分も人も大切にできる人間に育つそうです。
子どもが泣いて困るとき、
自分も 泣き言を言いたくなった時は
思い出してくださいね

「上手に甘えて 上手に泣くことは大切なこと」 ですよ

2017年06月13日
子どもの紫外線対策
こんにちは しんしろ助産所です
良いお天気が続いていますね。
隣接の児童館の園地で、ブランコや滑り台で遊ぶ子どもたちを
毎日のように見かけます。
ただ、これからの季節は紫外線がますます強くなるので
外で遊ぶ場合には、その影響を受けすぎないように注意したいものです。
かつては健康のバロメーターだった日焼けも、
今では紫外線を浴びすぎることによる有害性が指摘されています。
乳幼児の肌は刺激に弱いのが特徴。
強い日焼けを繰り返すと、シミやしわ、免疫力の低下や、皮膚がん
の原因にもなります。
強い日差しや長時間、紫外線の影響を受けることがないように
しましょう。
生活上の注意には
1. 陽ざしの強い10時から14時までの外出をはできるだけ避ける
2. 日陰を選ぶ
3. 肌の露出が少ない服装にする
4. つばの広い帽子をかぶる
等の他に
海や山など陽射しが強い場所では
子ども用の日焼け止めクリームも有用です。
(事前に腕の内側にぬって、痒みや発赤がでないか様子をみましょう。)
紫外線を通しにくい素材を使った衣類も販売されています。
日焼けで肌が赤くなってしまったら放置せず
まずは氷水で絞った冷たいタオルで冷やし、水疱になったり、症状が
よくならないような場合は病院へ。
ただ、子どもは外でもしっかりと遊ばせたいもの
紫外線対策ばかりにかまけていては、上手くいきません。
紫外線の有害性が勝らないように、ほどほどの対策を続けましょう。
 「6/15 子どもの救急」勉強会のお知らせ
「6/15 子どもの救急」勉強会のお知らせ

2017年06月12日
虫よけ対策

梅雨に入りましたが、今日は快晴

太陽がまぶしく、風が心地よい日です。こんな日は、お出かけしたくなりますね。
さて、この季節気になるのが虫
人間も虫もあたたかくなると活動が盛んになります。
外出するにも、気になるのは虫刺され

赤ちゃんや小さいお子さんのいる方はなおさらですね。
赤ちゃんの肌はやわらかいので、虫に刺されると真っ赤になったり、
腫れあがったり…
夏に出る虫の多くは、
『人や動物が出す、体温や湿度、汗に含まれる物質等に反応する』 ため。
新陳代謝が盛んで体温が高く汗をかきやすい赤ちゃんは、
大人に比べて虫にさされやすいといえます。
だからこそ、肌を出すことの多いこの時期は虫よけ対策が重要

対策としては
①外出時には、肌の露出部分を少なくする
②黒っぽい服装を避ける
③虫よけスプレーやローションの利用
④汗をこまめにふく
⑤水たまりや池などを避ける
⑥朝や夕方などの虫の出る時間帯には外出を避ける
等があげられます。
③の市販の虫よけには、スプレータイプのもの、シールタイプのもの、塗るタイプのもの、
つりさげるタイプのもの、ベビーカーやベッドに蚊帳のようなネットを
かけるもの、蚊取りマットや線香
 などもあります。
などもあります。色々あって、赤ちゃんや子どもに使うには抵抗を感じる方も
みえるのではないでしょうか。
一般的に虫よけに使われる『ディート』という成分は、
6か月未満の乳児に使用しない、生後6か月~2歳未満の子どもの使用は1日1回、
2~12歳未満の子どもでも1日3回までなど、月齢や年齢での使用制限があります。
赤ちゃんや子どもに使う場合は、成分や注意書きをしっかり確認しましょう。
赤ちゃんの虫よけには、ディート不使用の天然由来のものがベスト。
天然ハーブやアロマ由来のものは、肌がデリケートな赤ちゃんにも安心です

アロマやハッカ油を使い、自分で作ることもできます。
いつどこで虫に刺されるかわかりません。
早めの対策で虫刺されを予防し、お肌を守りましょう。

2017年06月09日
スキンケアは大切です!

食物アレルギーとアトピー性皮膚炎は
それぞれ別の病気ですが、
乳幼児は合併することがよくあります。
食物アレルギーを持つ0歳児の50%程度が
アトピー性皮膚炎の診断を受けているそうです。
湿疹や乾燥によってバリア機能が低下した
アトピー性皮膚炎の肌を通して
食物アレルギーが発症する、
と近年では考えられています。
つまりバリア機能が低下した皮膚では、
通常では通り抜けることのない大きな物質も
通り抜けてしまうため、
アレルギーを発症しやすいのだそう。
新生児期からスキンケアを丁寧に続けた場合、
乳幼児期の食物アレルギー発症が
およそ30%程度減少したという報告もあります。
時々、子どものアレルギーを予防するために
妊娠中・授乳中に卵や牛乳などを避ける人がいますが、
予防目的の自己判断による摂取制限は危険です。
それよりも食物アレルギーを予防するためには、
保湿などのスキンケアを継続し、
皮膚のバリア機能を保持することが大切なのですね。
また、アトピー性皮膚炎を発症した場合
ステロイド外用薬などが処方されることがあります。
でも、ステロイドの副作用を心配してか
「使用したくない」「良くなってきているので中止した」
とおっしゃるお母さんをよく見かけます。
実は処方された外用薬で
大きな副作用が出ることは ほとんどありません。
むしろ、自己判断で使用をやめてしまったり
指示された回数や量を守らずに 減量してしまうと
抑えられていた症状が悪化することがあり、
結果として症状が長引いてしまうことがあります。
ステロイドをやめるタイミングや
徐々に減らしていくタイミングは 自己判断せず
必ずかかりつけの医師の指示に従いましょう

 「子どもの救急」勉強会のお知らせ
「子どもの救急」勉強会のお知らせ

2017年06月08日
卒乳後おっぱいが小さくなった!?

妊娠・出産に伴って大きくなった胸も
授乳期を終えると、
妊娠前よりも小さくなったかも・・・

垂れてしまった・・・

と感じているママは多いかもしれません。
どうして卒乳後は
胸が小さくなったり、垂れてしまったと
感じるのでしょうか。
その理由は・・・
1)乳腺と脂肪の衰退
授乳期を終えると、
母乳を生成するホルモンが分泌されなくなるため
乳腺が衰退します。乳腺の周りについていた
脂肪も落ちるため、胸全体が小さくなります。
2)クーパー靭帯の伸展や切断
クーパー靭帯とは、乳腺と筋肉や皮膚をつないで胸を支えているもの。
妊娠・出産で胸が大きくなると、その重みや揺れによって
クーパー靭帯が伸びたり、中には急激な変化により
切れてしまうこともあるそう。
切れた靭帯は元には戻らず、伸びた靭帯もなかなか
元には戻らないため、垂れてしまう原因となります。
3)加齢
クーパー靭帯はコラーゲン繊維の束でできています。
年齢とともにコラーゲンが減ることでクーパー靭帯が衰えたり、
皮膚がたるむのもひとつの原因です。
4)日常生活の影響
・ブラのサイズが合っていない
・ブラをつけている時間が短い、寝る時はつけない
・猫背など姿勢が悪い
なども、クーパー靭帯の伸展や切断に影響します。
こういった妊娠・出産による体の変化は
ある程度は仕方のないことかもしれません。
それでもできる対策としては
こんなことがあります。
●サイズの合ったブラをつける。
●夜もスポーツブラやナイトブラを使用する。
●筋トレで大胸筋・小胸筋を鍛える。
(クーパー靭帯の負担を軽減します)
*背筋を伸ばし、両手の平を胸の前で合わせ、肘を水平に保ちます。
両手の平を中央に向かって強く押し、10秒キープします。
これを1日に何回か行う。
●姿勢を改善する。
●保湿して弾力・ハリを保つ。
●イソフラボンを摂取する。
(女性ホルモンと似た働きをします)
大豆・豆腐・納豆など
仕方がない・・・とあきらめずに
試してみませんか

 「子どもの救急」勉強会のお知らせ
「子どもの救急」勉強会のお知らせ
クリックすると画像が拡大します。

2017年06月07日
妊娠中に気をつけたい食べ物
こんにちは しんしろ助産所です
妊娠すると味覚が変わってすっぱいものが食べたくなったり
それまで好きだった食べ物が嫌いになったり…という経験はありませんか。
でも、妊娠するとすっぱいものが食べたくなるというのは俗説のようです。
私もつわりの時はミカンなら食べることができたけど
酸っぱいものはむしろ苦手でした。
ただ、私たちの身体は、妊娠すると徐々に濃い味や甘い味を好むように
になっているのだそう。
塩分や糖分の取りすぎは問題ですが、適度に塩分を取り込むことで
身体の水分量(循環血液量)を増やしたり、食欲を維持して胎児発育を
促す生理的な変化です。
取りすぎると害になるビタミンA のような栄養素もあります。
ビタミンAは必須ビタミンで体内に蓄積されやすく、過剰に食べても
平素は腹痛や下痢をしてお終いですが、妊娠初期には胎児奇形のリスクが
高まる(×3.7倍)ことが知られており、過剰摂取は禁物!
レバーに多く含まれますが、サプリメントや総合ビタミン剤により
過剰に摂取してしまうこともあるので気をつけましょう。
反対に、摂取を心がけたい栄養素は葉酸やビタミンDなど。
葉酸は妊娠初期の欠乏で神経管閉鎖障害をおこすリスクが高まることが
分かっており、妊娠前から摂取を心がけたいものです。
ビタミンDは魚やキノコ類を摂取し、日光浴などによって体内で合成されます。
一日に30分程度、週2,3回は日に当たることが必要といわれており、
過度な防御は赤ちゃんではクル病になるなどかえって有害。
栄養素は、それだけ食べたり摂ったら万全 というようなものはなく、
というようなものはなく、
過剰な摂取も制限も有害になることがあります。
生活していればいろんな日がありますが、概ね栄養が偏らないよう、
いろんな食品から栄養をとることが大切ですね。
2017年06月06日
良い(いい)加減の育児

子育て中のママ、毎日お疲れ様です。
普段の生活の中でも、『あれをやって、これもやって・・・』 と
次にやることを考えながらの忙しい日々をお過ごしのことと思います。
今は、子育てに関しても、色々な情報が満ちあふれているため、
『子どものために良いと思われることは何でもやらなきゃ』 と
ママが頑張りすぎて疲れていないか心配です。
そんなママが少しでも楽になるためには、
やらないことを決めること

『エッ
 』 と思うかもしれません。
』 と思うかもしれません。でも、家事に育児、さらにお仕事もあれば、24時間はあっという間。
ママは寝る時間を削って家族のために頑張っていますが、
それでは疲れはどんどんたまる一方

毎日そんな感じでは、身体も心も疲弊してしまいます。
やらないと決めることは、なかなか難しいことかもしれません。
でもママが疲れてストレスを感じていては、笑顔
 にもなれないですよね。
にもなれないですよね。子どもはママのことが大好き

ママが落ち着いて笑顔だと、子どもは心が満たされ、
安定した状態でいることができます。
たとえば、今日は食器はつけとくだけ~、今日は掃除も洗濯もお休み、
または、今日は子どもと一緒に寝ちゃう日
 などでもいいのです。
などでもいいのです。やらなきゃと思ってできないとストレスですが、やらないと決めればそれで良し

そうすれば、気分も楽になり、翌日の活気につながります。
人間って頑張ってしまうものですが、頑張らない日を決めるのも大切

まだまだ長く続く子育て、適度に息抜きしながら、
良い(いい)加減で過ごしてくださいね


2017年06月02日
「過保護」 と 「過干渉」

「過保護」 という言葉に
マイナスイメージを持つ人は多いと思います。
「あの子は過保護に育ったので、自分勝手でわがまま!」
という表現はよく聞かれます。
でも過保護は本当に良くないことなのでしょうか?
以前講演会で 「過保護と過干渉」 について
話を聞く機会がありました。
それがとても分かりやすいお話だったので
最近読んだ文献と合わせて 少しご紹介したいと思います。
「過保護」 と 「過干渉」 は似ているようで全く違います。
「過保護」 は子どもが望んでいることをやってあげること
「過干渉」 は子どもが望んでいないことをやりすぎることだそうです。
 」
」保護によって欲求が満たされ、満足した子どもの自立が早いのに対し、
干渉されすぎた子は 自立の芽が摘みとられ
自主性、主体性を損ねてしまいます。
ただ、親には子どもをしつける義務があるので
このさじ加減が一番難しいところ・・・

でも、愛情を持っている限り
修復はきくと信じています!
「子どもの欲求をたくさんかなえてあげ、
子どもが願ったとおリの愛し方をする。
これが保護であり、過保護であっても、ちっともかまわない。
そして満たされている子どもには、ある程度の干渉もできます。」
とのこと。
子どもの気持ちを考えない
親中心の過干渉にならないよう




