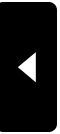2023年11月02日
安楽な育児って?
こんにちは しんしろ助産所です
現在オンラインで研修を受けています。
その中に「母子にとっての安楽な育児を考える」
というテーマがありました。
その中でみなさんにお伝えしたい内容を
少しご紹介したいと思います。
「産後1年まで続く身体症状」
産後1ヵ月でだんだん元の生活に戻して・・・
と言われがちですが、実際には
産後1年たっても80%の方に体の不調が続くそうです。
特に肩こりや腰痛、疲労などは
時間経過とともに増加傾向にあると言います。
痛みや疲れは目に見えないため
周りも気づきにくいのが現状です。
家族の皆さんもママを労わり、協力してあげてくださいね。
また、産後ケアや家事支援などを上手に利用し、
心身を休める機会を作りましょう。
「わかりにくい育児の大変さ」
●母親なら当たり前
●子どもの安全と責任は母親にある
●子育てに苦労はつきもの
という考え方が日本には定着していますが
育児を楽しいと思えるには3つの余裕が必要だそうです。
<時間>
●夫・家族・その他の人との分業
●しなくて良いことはしない
●家事の合理化(掃除ロボット、時短調理機などの利用も)
<心>
●不安や心配を一人で抱え込まない
●周囲に相談できる環境
<身体>
●産後ケアを受ける
●家族のサポートを得る
●公的支援の活用
ありきたりなことかもしれませんが、
●とにかく助けを求めていいこと
●我慢しすぎなくていいこと
●楽をするのは悪いことではないこと
などを覚えておいてもらえるといいかな、と思います。
「楽をしたらいい母親になれない」なんてことはありませんし、
心と身体に余裕ができて
「子育てが楽しい!子どもがかわいい♪」
と思えた方が親子にとって幸せなことですよね。
自分のことも大切にして
自分をもっと褒めてあげてください。
周りのみんなも、ママのことをもっと褒めてあげてください。
助産所にも褒められに来てくださいね

現在オンラインで研修を受けています。
その中に「母子にとっての安楽な育児を考える」
というテーマがありました。
その中でみなさんにお伝えしたい内容を
少しご紹介したいと思います。
「産後1年まで続く身体症状」
産後1ヵ月でだんだん元の生活に戻して・・・
と言われがちですが、実際には
産後1年たっても80%の方に体の不調が続くそうです。
特に肩こりや腰痛、疲労などは
時間経過とともに増加傾向にあると言います。
痛みや疲れは目に見えないため
周りも気づきにくいのが現状です。
家族の皆さんもママを労わり、協力してあげてくださいね。
また、産後ケアや家事支援などを上手に利用し、
心身を休める機会を作りましょう。
「わかりにくい育児の大変さ」
●母親なら当たり前
●子どもの安全と責任は母親にある
●子育てに苦労はつきもの
という考え方が日本には定着していますが
育児を楽しいと思えるには3つの余裕が必要だそうです。
<時間>
●夫・家族・その他の人との分業
●しなくて良いことはしない
●家事の合理化(掃除ロボット、時短調理機などの利用も)
<心>
●不安や心配を一人で抱え込まない
●周囲に相談できる環境
<身体>
●産後ケアを受ける
●家族のサポートを得る
●公的支援の活用
ありきたりなことかもしれませんが、
●とにかく助けを求めていいこと
●我慢しすぎなくていいこと
●楽をするのは悪いことではないこと
などを覚えておいてもらえるといいかな、と思います。
「楽をしたらいい母親になれない」なんてことはありませんし、
心と身体に余裕ができて
「子育てが楽しい!子どもがかわいい♪」
と思えた方が親子にとって幸せなことですよね。
自分のことも大切にして
自分をもっと褒めてあげてください。
周りのみんなも、ママのことをもっと褒めてあげてください。
助産所にも褒められに来てくださいね

2023年10月06日
親離れと子離れ
こんにちは しんしろ助産所です
生まれてから長い間、一緒に過ごし
大事に育ててきた我が子は
いつまでたっても大切な存在です。
そんな幼かった子どもも
成長とともに自分でできることが増え、
自立心が芽生え、少しずつ親の手を離れていきます。
子どもが自分の手を離れていくことは
親としてとてもさみしいものですね。
そんな時が来てほしくないという気持ちを持つのも
自然なことかもしれません。
そう思う反面、
子どもが親にべったり甘えていたり、
依存しているのではと感じるような場合は
ちゃんと親離れできるのかと
心配になることもあるかもしれません。
親離れ・子離れは、成長過程において
欠かせない通過儀礼のようなもの。
そこがうまくいかないと
子どもが自分の意思を表せない、指示なしに動けない、
自分に自信を持てない、挫折に負けてしまうなど
主体性が育ちにくく、自立を妨げてしまうことがあります。
そこで、親離れ・子離れのために大事なポイントです
子どもに対しては・・・
・子どもの成長を認める
・子どもの力を信じる
・年齢に応じて自分で判断したり、決断できるよう
自立を促すはたらきかけをする
・子どもの意見を尊重する
親自身は・・・
・必要な干渉と過干渉を考える
・子どもも1人の人間だと意識する
・自分の時間を充実させる
十分に子どもの甘えを受け入れ、
親子の信頼関係をしっかり築く乳幼児期。
学校生活の中で社会性を育てていく学童期。
心身ともに成熟し自立へと向かう思春期。
それぞれの成長段階に応じて、少しずつ
親離れ・子離れへの心構えや意識の切り替えを
していきましょう。
適度な親子の関係を見つめ直しながら、
子どもの成長を温かく見守っていきたいですね

生まれてから長い間、一緒に過ごし
大事に育ててきた我が子は
いつまでたっても大切な存在です。
そんな幼かった子どもも
成長とともに自分でできることが増え、
自立心が芽生え、少しずつ親の手を離れていきます。
子どもが自分の手を離れていくことは
親としてとてもさみしいものですね。
そんな時が来てほしくないという気持ちを持つのも
自然なことかもしれません。
そう思う反面、
子どもが親にべったり甘えていたり、
依存しているのではと感じるような場合は
ちゃんと親離れできるのかと
心配になることもあるかもしれません。
親離れ・子離れは、成長過程において
欠かせない通過儀礼のようなもの。
そこがうまくいかないと
子どもが自分の意思を表せない、指示なしに動けない、
自分に自信を持てない、挫折に負けてしまうなど
主体性が育ちにくく、自立を妨げてしまうことがあります。
そこで、親離れ・子離れのために大事なポイントです

子どもに対しては・・・
・子どもの成長を認める
・子どもの力を信じる
・年齢に応じて自分で判断したり、決断できるよう
自立を促すはたらきかけをする
・子どもの意見を尊重する
親自身は・・・
・必要な干渉と過干渉を考える
・子どもも1人の人間だと意識する
・自分の時間を充実させる
十分に子どもの甘えを受け入れ、
親子の信頼関係をしっかり築く乳幼児期。
学校生活の中で社会性を育てていく学童期。
心身ともに成熟し自立へと向かう思春期。
それぞれの成長段階に応じて、少しずつ
親離れ・子離れへの心構えや意識の切り替えを
していきましょう。
適度な親子の関係を見つめ直しながら、
子どもの成長を温かく見守っていきたいですね

2023年08月10日
モロー反射で寝られない?!
こんにちは しんしろ助産所です
モロー反射とは、生まれたときから
赤ちゃんに備わっている原始反射のひとつ。
音や光、風、体の向き、温度変化などの
外部からの刺激に対し、
驚いたように両手足を大きく広げ、
その後抱きつくように手足を縮めます。
危険を予測できない赤ちゃんが
自分の身を守るため、
守って欲しいことを知らせるため、
運動機能を発達させるためなどと
言われています。
生まれた直後から見られ、
生後4ヶ月を過ぎると自然にみられなくなります。
時々、外部の刺激に対して敏感なためか
モロー反射が起きやすい子がいます。
そのせいで、なかなか寝つけなかったり、
眠ったと思っても反射が起きて
すぐに目が覚めてしまったり、
モロー反射が起きて泣いてしまい機嫌が悪かったり・・・

モロー反射とは、生まれたときから
赤ちゃんに備わっている原始反射のひとつ。
音や光、風、体の向き、温度変化などの
外部からの刺激に対し、
驚いたように両手足を大きく広げ、
その後抱きつくように手足を縮めます。
危険を予測できない赤ちゃんが
自分の身を守るため、
守って欲しいことを知らせるため、
運動機能を発達させるためなどと
言われています。
生まれた直後から見られ、
生後4ヶ月を過ぎると自然にみられなくなります。
時々、外部の刺激に対して敏感なためか
モロー反射が起きやすい子がいます。
そのせいで、なかなか寝つけなかったり、
眠ったと思っても反射が起きて
すぐに目が覚めてしまったり、
モロー反射が起きて泣いてしまい機嫌が悪かったり・・・
と、大変な思いをしているパパやママもみえます。
そんな時の対策は・・・
●外部刺激をなるべく減らす
・大きな音を出さないようにする
・エアコンや扇風機などの風が直接当たらないようにする
・直射日光や照明の明るさに気をつける
・寒い季節は温度差が少なくなるよう
寝具をあたためておく
●おくるみ等で包む
おくるみやバスタオルなどで きつすぎないように
優しく体を包むことで、反射が起こりにくくなります。
暑い時期は通気性の良いガーゼやパイルの
生地のものを選ぶといいですね。
●余裕があるときは抱っこを
ずっと抱っこをしているわけにもいきませんが、
余裕があるときは抱っこをして体を包んであげると
赤ちゃんも安心できますね。
モロー反射は正常な反応とはいえ、
眠れない・機嫌が悪いといった原因になってしまうのは
ママもパパも赤ちゃん自身もつらいもの。
反応を和らげることで、赤ちゃんも安心できて、
ママやパパの負担も軽減できるといいですね
そんな時の対策は・・・
●外部刺激をなるべく減らす
・大きな音を出さないようにする
・エアコンや扇風機などの風が直接当たらないようにする
・直射日光や照明の明るさに気をつける
・寒い季節は温度差が少なくなるよう
寝具をあたためておく
●おくるみ等で包む
おくるみやバスタオルなどで きつすぎないように
優しく体を包むことで、反射が起こりにくくなります。
暑い時期は通気性の良いガーゼやパイルの
生地のものを選ぶといいですね。
●余裕があるときは抱っこを
ずっと抱っこをしているわけにもいきませんが、
余裕があるときは抱っこをして体を包んであげると
赤ちゃんも安心できますね。
モロー反射は正常な反応とはいえ、
眠れない・機嫌が悪いといった原因になってしまうのは
ママもパパも赤ちゃん自身もつらいもの。
反応を和らげることで、赤ちゃんも安心できて、
ママやパパの負担も軽減できるといいですね

2023年08月03日
デンマークの赤ちゃんのお昼寝事情
こんにちは しんしろ助産所です
いつもラジオを聴きながら通勤しているのですが、
今日、聞いた話にはびっくりしました。
デンマークでは、赤ちゃんの昼寝は外でさせるのだそうです。
北欧のデンマークでは夏でも17℃程度と涼しいそうですが
冬には、氷点下になるそうです。
ただその時は、服の上にウールのセーター、ズボン、帽子、
さらにダウンのロンパースでくるみ、その上から毛布を掛けて、
カバーの付いたベビーカーへ。
そのような重装備をしたうえで、外でお昼寝をさせるそうです。
それでも
「風邪をひくんじゃないか」
「連れ去られるのではないか」
と心配になりますが、
デンマーク大使館によると
「外で寝かせた方が、室内にくらべて睡眠時間が
1.5~2倍に長くなるとの研究がある」そうです。
長く寝ることは子どもの成長にも、
親のゆとりにもつながると考えられています。
保健省でも
「マイナス10℃までは完全に安全」
と注意事項を周知しつつ、推奨しているようです。
また、治安も良いため、連れ去りの不安はないとのこと。
色々なお国柄があって、様々な子育ての方法がありますが、
少なくとも日本のこの暑さでは
外でお昼寝なんて絶対に無理!
ちょっとうらやましい気がします

いつもラジオを聴きながら通勤しているのですが、
今日、聞いた話にはびっくりしました。
デンマークでは、赤ちゃんの昼寝は外でさせるのだそうです。
北欧のデンマークでは夏でも17℃程度と涼しいそうですが
冬には、氷点下になるそうです。
ただその時は、服の上にウールのセーター、ズボン、帽子、
さらにダウンのロンパースでくるみ、その上から毛布を掛けて、
カバーの付いたベビーカーへ。
そのような重装備をしたうえで、外でお昼寝をさせるそうです。
それでも
「風邪をひくんじゃないか」
「連れ去られるのではないか」
と心配になりますが、
デンマーク大使館によると
「外で寝かせた方が、室内にくらべて睡眠時間が
1.5~2倍に長くなるとの研究がある」そうです。
長く寝ることは子どもの成長にも、
親のゆとりにもつながると考えられています。
保健省でも
「マイナス10℃までは完全に安全」
と注意事項を周知しつつ、推奨しているようです。
また、治安も良いため、連れ去りの不安はないとのこと。
色々なお国柄があって、様々な子育ての方法がありますが、
少なくとも日本のこの暑さでは
外でお昼寝なんて絶対に無理!
ちょっとうらやましい気がします

2023年07月13日
夏の授乳や抱っこの暑さ対策
こんにちは しんしろ助産所です
毎日蒸し暑いですね
いよいよ梅雨明けも間近のようです。
この時期、赤ちゃんと密着する授乳や抱っこは
暑さで不快に感じることも多いのではないでしょうか。
もともと体温の高い赤ちゃんは
授乳時にはさらに上がり、
特に頭や背中に汗をかきやすくなります。
一方、ママ自身も授乳時に分泌されるホルモンによって
体が熱くなり、汗をかきやすくなります。
肌が接触するママの腕や赤ちゃんの頭、首の後ろは
お互いの体温や汗で蒸れたり、ベタベタとくっついて
不快なうえに、あせもなどの皮膚トラブルを
起こしてしまうこともあります。
「おっぱいをあげても離して泣く」
「抱っこであやしても泣き止まない」
など、暑さが不機嫌の原因と思われる場合も・・・。
皮膚トラブルを防ぎ、少しでも快適に
授乳や抱っこができるような対策をしたいですね。
●空調を強めに涼しくしてから授乳する
●ママの腕にタオルやアームカバーをつける。
接触する部分の汗を吸収し不快感を軽減できます。
接触冷感素材のものもいいですね。
●赤ちゃんの背中に汗取りパッドやガーゼハンカチを入れる
そのまま寝てしまっても、
ガーゼハンカチを引きぬくだけで
着替えをしなくてもすみます。
●保冷剤や保冷シートを活用
アームカバーの下に保冷剤を入れたり、
抱っこひもの背中や赤ちゃんとママの間に
装着できる保冷シートなどの便利グッズもあるようです。
大事な赤ちゃんとの触れあいの時間。
少しでも快適に楽しく過ごしたいですね

毎日蒸し暑いですね

いよいよ梅雨明けも間近のようです。
この時期、赤ちゃんと密着する授乳や抱っこは
暑さで不快に感じることも多いのではないでしょうか。
もともと体温の高い赤ちゃんは
授乳時にはさらに上がり、
特に頭や背中に汗をかきやすくなります。
一方、ママ自身も授乳時に分泌されるホルモンによって
体が熱くなり、汗をかきやすくなります。
肌が接触するママの腕や赤ちゃんの頭、首の後ろは
お互いの体温や汗で蒸れたり、ベタベタとくっついて
不快なうえに、あせもなどの皮膚トラブルを
起こしてしまうこともあります。
「おっぱいをあげても離して泣く」
「抱っこであやしても泣き止まない」
など、暑さが不機嫌の原因と思われる場合も・・・。
皮膚トラブルを防ぎ、少しでも快適に
授乳や抱っこができるような対策をしたいですね。
●空調を強めに涼しくしてから授乳する
●ママの腕にタオルやアームカバーをつける。
接触する部分の汗を吸収し不快感を軽減できます。
接触冷感素材のものもいいですね。
●赤ちゃんの背中に汗取りパッドやガーゼハンカチを入れる
そのまま寝てしまっても、
ガーゼハンカチを引きぬくだけで
着替えをしなくてもすみます。
●保冷剤や保冷シートを活用
アームカバーの下に保冷剤を入れたり、
抱っこひもの背中や赤ちゃんとママの間に
装着できる保冷シートなどの便利グッズもあるようです。
大事な赤ちゃんとの触れあいの時間。
少しでも快適に楽しく過ごしたいですね

2023年06月30日
壁や床に頭をぶつける赤ちゃん
こんにちは しんしろ助産所です
子どもが生後8ヶ月頃、
壁の側に座って、自分で頭をゴチンゴチンと

子どもが生後8ヶ月頃、
壁の側に座って、自分で頭をゴチンゴチンと
壁にぶつけていることがありました。
同じような経験があるママもみえるかもしれません。
これは生後6ヶ月頃から比較的よくみられる
「ヘッドバンギング」といわれるもの。
壁だけでなく床にぶつけたり、
頭を前後や左右に振る・回す、
体を揺らすような場合もあり、
医学的には運動性習癖といわれます。
どうしてそんなことをするの?
と疑問に思われますよね。
その理由や状況はさまざまなようです。
●ぶつけるときの音や感覚を楽しんでいる
ゴチンゴチンとぶつけてはにこにこ。
我が家はこのパターンでした。
軽くぶつける程度で楽しそうにやっているので
同じような経験があるママもみえるかもしれません。
これは生後6ヶ月頃から比較的よくみられる
「ヘッドバンギング」といわれるもの。
壁だけでなく床にぶつけたり、
頭を前後や左右に振る・回す、
体を揺らすような場合もあり、
医学的には運動性習癖といわれます。
どうしてそんなことをするの?
と疑問に思われますよね。
その理由や状況はさまざまなようです。
●ぶつけるときの音や感覚を楽しんでいる
ゴチンゴチンとぶつけてはにこにこ。
我が家はこのパターンでした。
軽くぶつける程度で楽しそうにやっているので
むしろかわいらしい光景でした。
●気分を紛らわせたり、気持ちを落ち着かせている
眠いときやさみしいとき、不安なときなどに
やることが多いようです。
●かまってもらうため、注意を引くため
親の反応をみながらやっているのかもしれません。
●欲求不満やかんしゃくを和らげるため
怒られたり、思い通りにいかなかったりして
言葉では表現できない気持ちを
体で表現していることもあるようです。
ヘッドバンギングをするタイミングや状況、
強さや頻度、子どもの機嫌など
どんなときに、どんなふうにしているのか、
お子さんの様子をよくみてみましょう。
やめさせようと注意したりするのは
逆に癖になってしまうこともあるので
他の遊びや抱っこをするなどで
気をそらしてあげられるといいかもしれません。
成長とともに自然とおさまるので、
あまり心配せず見守ってあげるのがよいようです
●気分を紛らわせたり、気持ちを落ち着かせている
眠いときやさみしいとき、不安なときなどに
やることが多いようです。
●かまってもらうため、注意を引くため
親の反応をみながらやっているのかもしれません。
●欲求不満やかんしゃくを和らげるため
怒られたり、思い通りにいかなかったりして
言葉では表現できない気持ちを
体で表現していることもあるようです。
ヘッドバンギングをするタイミングや状況、
強さや頻度、子どもの機嫌など
どんなときに、どんなふうにしているのか、
お子さんの様子をよくみてみましょう。
やめさせようと注意したりするのは
逆に癖になってしまうこともあるので
他の遊びや抱っこをするなどで
気をそらしてあげられるといいかもしれません。
成長とともに自然とおさまるので、
あまり心配せず見守ってあげるのがよいようです

2023年06月23日
赤ちゃんからママへの思いやり!?
こんにちは しんしろ助産所です
赤ちゃんはうまれて2ヵ月位は夜型の生活です。
「なんで夜になると寝てくれないの?」
と悲しくなってしまうかもしれませんが
これには理由があるんです。
妊娠後期、夜になると胎動が多い!
と感じることはありませんでしたか?
赤ちゃんはお腹の中ではへその緒と胎盤を通じ、
ママから酸素をもらって生活していました。
ママの活動量が多い日中に赤ちゃんが活発に動くと
ママの体に負担がかかってしまうので、
夜間ママが休息している時間帯を選んで
活発に動くのだそうです。
赤ちゃんって優しい
ただ、生まれてすぐに昼型になるかというとそうではなく、
しばらくはお腹の中にいたときのリズムが残っているので
夜型になってしまうのですね。
一般的には在胎28週から生後8週頃が夜型で
その後昼型の生活に変わってゆくと言われています。
辛くなった時は
「これは赤ちゃんからママへの思いやり 」
」
「ゴールはもうじき‼」
と思うと少しは気持ちが楽になるかもしれませんね。
でも「もう限界!」となる前に、
家族にお願いして休息をとるのも大切です。
また、「産後ケア事業」や「家事育児支援」を利用するのも
1つの方法ですので、困った時は行政
(市役所・保健センター・助産所など)に相談してみてくださいね

赤ちゃんはうまれて2ヵ月位は夜型の生活です。
「なんで夜になると寝てくれないの?」
と悲しくなってしまうかもしれませんが
これには理由があるんです。
妊娠後期、夜になると胎動が多い!
と感じることはありませんでしたか?
赤ちゃんはお腹の中ではへその緒と胎盤を通じ、
ママから酸素をもらって生活していました。
ママの活動量が多い日中に赤ちゃんが活発に動くと
ママの体に負担がかかってしまうので、
夜間ママが休息している時間帯を選んで
活発に動くのだそうです。
赤ちゃんって優しい

ただ、生まれてすぐに昼型になるかというとそうではなく、
しばらくはお腹の中にいたときのリズムが残っているので
夜型になってしまうのですね。
一般的には在胎28週から生後8週頃が夜型で
その後昼型の生活に変わってゆくと言われています。
辛くなった時は
「これは赤ちゃんからママへの思いやり
 」
」「ゴールはもうじき‼」
と思うと少しは気持ちが楽になるかもしれませんね。
でも「もう限界!」となる前に、
家族にお願いして休息をとるのも大切です。
また、「産後ケア事業」や「家事育児支援」を利用するのも
1つの方法ですので、困った時は行政
(市役所・保健センター・助産所など)に相談してみてくださいね

2023年06月16日
手を口に入れるのは空腹のサイン?!
こんにちは しんしろ助産所です
納豆ご飯に何を足す? にコメントを頂きました。
ありがとうございます
これを足したら美味しかったよ
というご意見をお伺いしたところ、
「すりごまとお酢や鰹節、生卵など。
特にお酢は付属のタレにプラスで大さじ1~2くらい
ドバドバと入れるのがおすすめ」だそう。
みなさんもぜひお試しくださいね。
さて、生後3ヶ月頃になると
自分の手を口に入れるようになる赤ちゃんが
増えてきます。
指やこぶしをチュパチュパとなめたり、
吸ったりする様子を見ると、
お腹がすいたのかな
と思われる方も多いのではないでしょうか。
授乳した後に見られると
足りないのかな
と心配になってしまうこともあるかもしれません。
確かに、お腹がすいたときに
そのようなサインが見られることがあります。
ただ、そうではないこともよくあります。
指や口を手に入れるのは
「赤ちゃんの初めての一人遊び」
とも言われます。
自分の手をじーっと見つめる
ハンドリガードが見られた後、
少しするとそれを口に入れるようになり
目や口で自分の手・指を認識し
感覚を養っていくためです。
そうしているうちに
うまく指が入って指しゃぶりが始まる子も・・・
必ずしも空腹のサインではないとすると
授乳のタイミングに悩んでしまうこともあるかもしれません。
前回の授乳の様子(飲み具合など)や時間、
機嫌なども合わせて判断し、
はっきりしなければ授乳タイムにしてみるのも
ひとつの方法です。
赤ちゃんは日々成長していきます。
気になること、心配なことなどあれば
お気軽にご相談ください

納豆ご飯に何を足す? にコメントを頂きました。
ありがとうございます

これを足したら美味しかったよ

というご意見をお伺いしたところ、
「すりごまとお酢や鰹節、生卵など。
特にお酢は付属のタレにプラスで大さじ1~2くらい
ドバドバと入れるのがおすすめ」だそう。
みなさんもぜひお試しくださいね。
さて、生後3ヶ月頃になると
自分の手を口に入れるようになる赤ちゃんが
増えてきます。
指やこぶしをチュパチュパとなめたり、
吸ったりする様子を見ると、
お腹がすいたのかな

と思われる方も多いのではないでしょうか。
授乳した後に見られると
足りないのかな

と心配になってしまうこともあるかもしれません。
確かに、お腹がすいたときに
そのようなサインが見られることがあります。
ただ、そうではないこともよくあります。
指や口を手に入れるのは
「赤ちゃんの初めての一人遊び」
とも言われます。
自分の手をじーっと見つめる
ハンドリガードが見られた後、
少しするとそれを口に入れるようになり
目や口で自分の手・指を認識し
感覚を養っていくためです。
そうしているうちに
うまく指が入って指しゃぶりが始まる子も・・・
必ずしも空腹のサインではないとすると
授乳のタイミングに悩んでしまうこともあるかもしれません。
前回の授乳の様子(飲み具合など)や時間、
機嫌なども合わせて判断し、
はっきりしなければ授乳タイムにしてみるのも
ひとつの方法です。
赤ちゃんは日々成長していきます。
気になること、心配なことなどあれば
お気軽にご相談ください

2023年05月17日
赤ちゃんの目のゴミ
こんにちは しんしろ助産所です
赤ちゃんの目の中に
ゴミやほこりが入っているのを見つけ
痛いんじゃないかな
早く取ってあげたいけどどうしたらいいの
と困ってしまうことがあります。
ゴミやほこりが目に入るのを
防いでくれるのが“まつげ”ですが、
赤ちゃんのまつげは成長とともに伸びてくるので
生まれた時にはまだ生えそろっていません。
そのため生後間もないうちはゴミやほこりが
入りやすくなってしまいます。
また、寝ていることの多い赤ちゃんですが
起きて目を開けているときは瞬きが少ないのも原因のひとつ。
赤ちゃんはまだ視力が弱く、焦点を合わせるのに
時間がかかるためなのだそう。
さらに、反射的に目を閉じる機能も
生後2~3ヶ月頃までは発達していません。
ただその分、目を保護する涙の分泌が多く
大人よりも潤っているのだそう。
ゴミやほこりを見つけたら
すぐにでも取ってあげたいものですが
無理に取ろうとすると
目を傷つけてしまうことがあります。
基本的には目を保護する涙で自然に流されるので
何もしなくても大丈夫です。
ただ、目に入ったゴミが
先の尖ったものや硬いもので
放置すると目を傷つけそうなものだったり、
赤ちゃんが目を気にして触ろうとする、
機嫌が悪い、充血している・・・
といった場合は眼科で診てもらいましょう

赤ちゃんの目の中に
ゴミやほこりが入っているのを見つけ
痛いんじゃないかな

早く取ってあげたいけどどうしたらいいの

と困ってしまうことがあります。
ゴミやほこりが目に入るのを
防いでくれるのが“まつげ”ですが、
赤ちゃんのまつげは成長とともに伸びてくるので
生まれた時にはまだ生えそろっていません。
そのため生後間もないうちはゴミやほこりが
入りやすくなってしまいます。
また、寝ていることの多い赤ちゃんですが
起きて目を開けているときは瞬きが少ないのも原因のひとつ。
赤ちゃんはまだ視力が弱く、焦点を合わせるのに
時間がかかるためなのだそう。
さらに、反射的に目を閉じる機能も
生後2~3ヶ月頃までは発達していません。
ただその分、目を保護する涙の分泌が多く
大人よりも潤っているのだそう。
ゴミやほこりを見つけたら
すぐにでも取ってあげたいものですが
無理に取ろうとすると
目を傷つけてしまうことがあります。
基本的には目を保護する涙で自然に流されるので
何もしなくても大丈夫です。
ただ、目に入ったゴミが
先の尖ったものや硬いもので
放置すると目を傷つけそうなものだったり、
赤ちゃんが目を気にして触ろうとする、
機嫌が悪い、充血している・・・
といった場合は眼科で診てもらいましょう

2023年05月10日
赤ちゃんをSIDS(乳幼児突然死症候群)から守ろう
こんにちは しんしろ助産所です
厚労省でも「1歳までは寝かせるときは仰向けに」
と言っているように、うつぶせ寝をすると
SIDS(乳幼児突然死症候群)のリスクが高くなります。
そのため、寝返りをうつようになると
その成長がうれしい反面
心配になってしまう方もみえます。
その時期の質問で多いのが
「気づいたらうつぶせで寝ていた場合は
元に戻した方が良いでしょうか?」というもの。
SIDSの発生頻度は出生6000~7000人に1人で、
まれに1歳以上で発症することもありますが
生後2~6か月に多いのが特徴です。
アメリカではうつぶせになった児を
仰向けにする必要はないとしています。
その理由は寝返りできる年齢になった後は
リスクが下がるためだそう。
確かに寝返りがえりが上手にできる頃には
SIDSの可能性は低くなりますが
まだ寝返りが上手にできない頃や
仰向け寝推奨の1歳未満の場合は
仰向けに直してあげる方が安心な気がします。
ただSIDSはうつぶせ寝だけでなく
さまざまな因子が重なって起こると言われています。
●養育者の喫煙(特に母親)
●重い布団
●ベッド周囲の枕や玩具
●身体が沈むような柔らかい布団
などもリスク因子とされています。
うつぶせ寝だけでなく、環境を整えることで
赤ちゃんをSIDSから守りましょう

厚労省でも「1歳までは寝かせるときは仰向けに」
と言っているように、うつぶせ寝をすると
SIDS(乳幼児突然死症候群)のリスクが高くなります。
そのため、寝返りをうつようになると
その成長がうれしい反面
心配になってしまう方もみえます。
その時期の質問で多いのが
「気づいたらうつぶせで寝ていた場合は
元に戻した方が良いでしょうか?」というもの。
SIDSの発生頻度は出生6000~7000人に1人で、
まれに1歳以上で発症することもありますが
生後2~6か月に多いのが特徴です。
アメリカではうつぶせになった児を
仰向けにする必要はないとしています。
その理由は寝返りできる年齢になった後は
リスクが下がるためだそう。
確かに寝返りがえりが上手にできる頃には
SIDSの可能性は低くなりますが
まだ寝返りが上手にできない頃や
仰向け寝推奨の1歳未満の場合は
仰向けに直してあげる方が安心な気がします。
ただSIDSはうつぶせ寝だけでなく
さまざまな因子が重なって起こると言われています。
●養育者の喫煙(特に母親)
●重い布団
●ベッド周囲の枕や玩具
●身体が沈むような柔らかい布団
などもリスク因子とされています。
うつぶせ寝だけでなく、環境を整えることで
赤ちゃんをSIDSから守りましょう

2023年04月13日
子どもの足の爪が反り返っている!?
こんにちは しんしろ助産所です
ここ最近続けて質問のあった、
子どもの足の爪のこと。
足の爪、特に親指の爪が上向きに反り返っていて
「これって普通ですか?」
とママが心配されてのことでした。
赤ちゃんの爪はとても薄く、
ハイハイをしたり、つかまり立ちをすると
つま先に圧がかかり、その刺激で爪が変形したり
割れたりしやすくなります。
そのため、生後半年~3才頃までは
反り返ったような形になっていることが
少なくありません。
質問のあったママも
「友達に話したら、その子の子どもも同じような爪をしてた」
とのこと。
成長とともに爪も次第に厚くなり
形もだんだんと整ってきます。
それまでは、反り返った爪は
伸びると引っかかりやすいので、
こまめに切ってあげてくださいね

ここ最近続けて質問のあった、
子どもの足の爪のこと。
足の爪、特に親指の爪が上向きに反り返っていて
「これって普通ですか?」
とママが心配されてのことでした。
赤ちゃんの爪はとても薄く、
ハイハイをしたり、つかまり立ちをすると
つま先に圧がかかり、その刺激で爪が変形したり
割れたりしやすくなります。
そのため、生後半年~3才頃までは
反り返ったような形になっていることが
少なくありません。
質問のあったママも
「友達に話したら、その子の子どもも同じような爪をしてた」
とのこと。
成長とともに爪も次第に厚くなり
形もだんだんと整ってきます。
それまでは、反り返った爪は
伸びると引っかかりやすいので、
こまめに切ってあげてくださいね

2023年03月29日
昼間はなるべく起こしておいた方がいい?
こんにちは しんしろ助産所です
「赤ちゃんが夜よく眠れるように
昼間はなるべく起こしておいた方がいいの 」
」
と聞かれることが時々あります。
生後間もない時期はまだ昼と夜の認識もなく、
寝たり、起きたりを短時間で繰り返します。
その後、成長とともに
だんだんと昼間起きている時間が長くなったり、
夜に眠る時間が長くなってきます。
ただ、睡眠のリズムは十人十色。
昼間あまり寝ない子、よく寝る子、
夜も生後数ヶ月から朝までぐっすり寝る子もいれば、

「赤ちゃんが夜よく眠れるように
昼間はなるべく起こしておいた方がいいの
 」
」と聞かれることが時々あります。
生後間もない時期はまだ昼と夜の認識もなく、
寝たり、起きたりを短時間で繰り返します。
その後、成長とともに
だんだんと昼間起きている時間が長くなったり、
夜に眠る時間が長くなってきます。
ただ、睡眠のリズムは十人十色。
昼間あまり寝ない子、よく寝る子、
夜も生後数ヶ月から朝までぐっすり寝る子もいれば、
1歳を過ぎても数時間おきに起きる子など
個人差が大きいものです。
昼間によく寝たからといって
夜に寝ないともかぎりません。
昼間になるべく起こそうとすると
眠くてぐずってしまいかえって大変になることも・・・
眠いようなら寝かせ、
長く寝ているからと起こす必要はありません。
自然な眠りを妨げないよう
赤ちゃん自身のリズムに合わせてあげるのが一番です。
そうしているうちに、その子なりの
睡眠のリズムができてきます。
ただ、新生児期は夜に寝てもらうためではなく、
必要な栄養を摂って、順調に発育できるよう
起こす必要がある場合もあります。
よく寝るからいいと思っていたら
授乳回数が減り、体重の増えが
少なくなっているケースです。
3~4時間以上よく寝る場合は、一度
体重の増えや哺乳量を確認できると安心ですね。
昼間は窓際で陽の光をあびたり、散歩をしたり
夜にはある程度の時間を決めて
お風呂に入り、部屋を暗くして寝る・・・
個人差が大きいものです。
昼間によく寝たからといって
夜に寝ないともかぎりません。
昼間になるべく起こそうとすると
眠くてぐずってしまいかえって大変になることも・・・

眠いようなら寝かせ、
長く寝ているからと起こす必要はありません。
自然な眠りを妨げないよう
赤ちゃん自身のリズムに合わせてあげるのが一番です。
そうしているうちに、その子なりの
睡眠のリズムができてきます。
ただ、新生児期は夜に寝てもらうためではなく、
必要な栄養を摂って、順調に発育できるよう
起こす必要がある場合もあります。
よく寝るからいいと思っていたら
授乳回数が減り、体重の増えが
少なくなっているケースです。
3~4時間以上よく寝る場合は、一度
体重の増えや哺乳量を確認できると安心ですね。
昼間は窓際で陽の光をあびたり、散歩をしたり
夜にはある程度の時間を決めて
お風呂に入り、部屋を暗くして寝る・・・
という生活リズムも大事なのかもしれません。
その子なりの睡眠をサポートしてあげたいですね

2023年03月16日
赤ちゃんのロンパース
こんにちは しんしろ助産所です
上下つながっている赤ちゃんのロンパース
ただセパレートにすると、
「おむつ替えのたびに脱がしたり、はかせたりするのが大変」
と話すママも
赤ちゃんが動きやすく、ママが楽なのを選ぶといいですね。
上下つながっているロンパースはおなかが出ることがなく
冷え対策にもなるためパジャマとしては活躍しそうです。
セパレートにしてからでも、サイズの合うロンパースがあれば


上下つながっている赤ちゃんのロンパース

赤ちゃんらしくてかわいいですね

時折、ママさんから
「ロンパースっていつまで着せたらいい?」
ときかれることがあります。
「ロンパースっていつまで着せたらいい?」
ときかれることがあります。
結論としては、「ママの考え次第でいいです」
今では上下つながっていても、はたから見ると
今では上下つながっていても、はたから見ると
セパレートのようなデザインのものもあるし、
サイズも80や90のものも売っています。
赤ちゃんの身体にあっていれば、特に決まりはありません。
ロンパースからセパレートに変えたママは
「ハイハイをするようになって動きにくそうだっだ 」
」
「ボタンがたくさんあってとめるのが大変」
「かわいくて好きだったけど、動き回ってボタンがとめられない」
「上下どちらかだけ着替えたいときに面倒」
等が理由だそうです。
赤ちゃんの身体にあっていれば、特に決まりはありません。
ロンパースからセパレートに変えたママは
「ハイハイをするようになって動きにくそうだっだ
 」
」「ボタンがたくさんあってとめるのが大変」
「かわいくて好きだったけど、動き回ってボタンがとめられない」
「上下どちらかだけ着替えたいときに面倒」
等が理由だそうです。
ただセパレートにすると、
「おむつ替えのたびに脱がしたり、はかせたりするのが大変」
と話すママも

赤ちゃんが動きやすく、ママが楽なのを選ぶといいですね。
上下つながっているロンパースはおなかが出ることがなく
冷え対策にもなるためパジャマとしては活躍しそうです。
セパレートにしてからでも、サイズの合うロンパースがあれば
夜間の就寝時に使ってみてはいかがでしょうか


2023年03月03日
花粉の時期は赤ちゃんの散歩を控えた方がいいの?
こんにちは しんしろ助産所です
まだまだ寒い日もありますが
春の気配が感じられるようになってきました。
暖かくなるのはうれしいけれど
花粉に悩まされる方にとっては辛い時期
今年の花粉の飛散量は例年より多いと言われているので
余計に憂鬱になってしまいますね。
この時期、赤ちゃんのいるご家庭では
暖かい日は散歩日和なのに
「赤ちゃんを連れて散歩に出かけない方がいいの?」
「花粉症になってしまう?」
と花粉の影響が心配になってしまう方が多くみえます。
花粉症の発症は、
生まれて最初のシーズンで花粉に触れ
次のシーズンを経験してからでないと
発症しないと言われていましたが、
遺伝によるアレルギーの素因などにより
乳幼児期でも発症しないとは限らないのだそう。
花粉症予防のためには、
できるだけ花粉に触れないのがベストですが
ずっと家にこもっている訳にもいきません。
散歩や外出は気分転換や感覚を刺激して
発達を促す効果もあります。
そのため、外出時にはなるべく花粉の影響を
減らせるように対策をしましょう。
●飛散量の多い日は外出を控える。
風が強い日・気温の高い日・湿度の低い日
雨が降った次の日など、花粉情報も参考に。
●飛散量の多い時間を避ける。
お昼前後と日没前後は多い(天気や地域による)
●帽子・ベビーカーのほろなどでできるだけ
花粉を浴びないようにする。
●花粉が付着しにくいつるつるした素材の服を選ぶ。
●短時間にする
●帰宅したら手や顔の周りを拭いてあげる
赤ちゃんにもできる対策をして
楽しく散歩に出かけられるといいですね

まだまだ寒い日もありますが
春の気配が感じられるようになってきました。
暖かくなるのはうれしいけれど
花粉に悩まされる方にとっては辛い時期

今年の花粉の飛散量は例年より多いと言われているので
余計に憂鬱になってしまいますね。
この時期、赤ちゃんのいるご家庭では
暖かい日は散歩日和なのに
「赤ちゃんを連れて散歩に出かけない方がいいの?」
「花粉症になってしまう?」
と花粉の影響が心配になってしまう方が多くみえます。
花粉症の発症は、
生まれて最初のシーズンで花粉に触れ
次のシーズンを経験してからでないと
発症しないと言われていましたが、
遺伝によるアレルギーの素因などにより
乳幼児期でも発症しないとは限らないのだそう。
花粉症予防のためには、
できるだけ花粉に触れないのがベストですが
ずっと家にこもっている訳にもいきません。
散歩や外出は気分転換や感覚を刺激して
発達を促す効果もあります。
そのため、外出時にはなるべく花粉の影響を
減らせるように対策をしましょう。
●飛散量の多い日は外出を控える。
風が強い日・気温の高い日・湿度の低い日
雨が降った次の日など、花粉情報も参考に。
●飛散量の多い時間を避ける。
お昼前後と日没前後は多い(天気や地域による)
●帽子・ベビーカーのほろなどでできるだけ
花粉を浴びないようにする。
●花粉が付着しにくいつるつるした素材の服を選ぶ。
●短時間にする
●帰宅したら手や顔の周りを拭いてあげる
赤ちゃんにもできる対策をして
楽しく散歩に出かけられるといいですね

2023年02月14日
チョコレートはいつからOK?
こんにちは しんしろ助産所です
今日はバレンタインデー。
ドキドキしながらチョコを用意することも
すっかりなくなりましたが
家族用と称して、
今年も自分の食べたいチョコを選びました。
そのチョコレートですが、
子どもに与える時期で迷うママも多いと思います。
いつからなら食べさせても良いのでしょうか?
結論から言うと
はちみつのように中毒をおこしたり
アレルギーを引き起こす可能性はあまりないため
チョコレートには「何歳から」という
明確な基準はないそうです。
ただ 砂糖がたくさん使われていること、
脂肪分が高く、消化機能が未熟な子どもには負担がかかること
依存性や覚醒作用のある成分も含まれている
などを考えると、少なくとも3歳以降が良いようです。
チョコレート味やココア風味の赤ちゃん用お菓子は、
1歳半ごろから徐々にOKといわれています。
そうは言っても、上の子にくらべて下の子は
チョコレートの味を覚えるのも早くなってしまいがちです。
一度知ってしまうと欲しい気持ちが
抑えられなくなってしまうため
できる限り遅めの時期、少なめの量から
与えるのが望ましいですね

今日はバレンタインデー。
ドキドキしながらチョコを用意することも
すっかりなくなりましたが
家族用と称して、
今年も自分の食べたいチョコを選びました。
そのチョコレートですが、
子どもに与える時期で迷うママも多いと思います。
いつからなら食べさせても良いのでしょうか?
結論から言うと
はちみつのように中毒をおこしたり
アレルギーを引き起こす可能性はあまりないため
チョコレートには「何歳から」という
明確な基準はないそうです。
ただ 砂糖がたくさん使われていること、
脂肪分が高く、消化機能が未熟な子どもには負担がかかること
依存性や覚醒作用のある成分も含まれている
などを考えると、少なくとも3歳以降が良いようです。
チョコレート味やココア風味の赤ちゃん用お菓子は、
1歳半ごろから徐々にOKといわれています。
そうは言っても、上の子にくらべて下の子は
チョコレートの味を覚えるのも早くなってしまいがちです。
一度知ってしまうと欲しい気持ちが
抑えられなくなってしまうため
できる限り遅めの時期、少なめの量から
与えるのが望ましいですね

2023年01月26日
育休明けの仕事復帰
こんにちは しんしろ助産所です
妊娠出産後、初めての仕事復帰予定のママさんは
「何を準備したらいいのか」
「復帰後の仕事の時間帯はどうなのか」
「子どもの病気などで急なお休みなどになったら大丈夫か」
「職場の理解は得られるか」 等など
周囲に育休明けの先輩などがいれば話を聞けますが、
先日お話ししたママは、小さな事業所で育休を取ったのは自分が初めてで
でも、厚労省の「育児・介護休業法」では時短勤務(短時間勤務制度)が認められています。
この法律のポイントは
・事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について

妊娠出産後、初めての仕事復帰予定のママさんは
復帰のことを考えると、不安なことがたくさんあると思います。
「何を準備したらいいのか」
「復帰後の仕事の時間帯はどうなのか」
「子どもの病気などで急なお休みなどになったら大丈夫か」
「職場の理解は得られるか」 等など
あげればきりがありません
色々な悩みを抱えていると、仕事へのモチベーションも上がりません。

色々な悩みを抱えていると、仕事へのモチベーションも上がりません。
周囲に育休明けの先輩などがいれば話を聞けますが、
先日お話ししたママは、小さな事業所で育休を取ったのは自分が初めてで
今後のことは不安だらけ と話していました。
と話していました。
 と話していました。
と話していました。保育園など預ける場所は決まっていても、子育てと仕事の両立を考えると
気持ちもせわしくなりそうですね。
ワーキングママに伺うと、
まずは、フルタイムで働くのか、時短勤務にするのかなど選択するそうですが
厚生労働省の調査によると、時短勤務の制度を導入している事業所は7割弱
気持ちもせわしくなりそうですね。
ワーキングママに伺うと、
まずは、フルタイムで働くのか、時短勤務にするのかなど選択するそうですが
厚生労働省の調査によると、時短勤務の制度を導入している事業所は7割弱

もしかしたら「所属企業には時短勤務の前例がない」ということもあるかもしれません。
でも、厚労省の「育児・介護休業法」では時短勤務(短時間勤務制度)が認められています。
この法律のポイントは
・事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について
従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければならない
・就業規則に規定されるなど、制度化された状態になっていることが必要であり、
・就業規則に規定されるなど、制度化された状態になっていることが必要であり、
運用で行われているだけでは不十分
・短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として
・短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として
6時間(5時間45分~6時間まで)とする措置をする
の3点で、たとえ前例がなくても仕事と育児の両立が必要な場合は
の3点で、たとえ前例がなくても仕事と育児の両立が必要な場合は
時短勤務を選択する権利がある ということです。
ということです。
ただし、時短勤務にすると手当や給与の面でどうしてもフルタイムより減少します。
前述した方は、色々悩み、職場や家族と相談し、フルタイムで4月から復帰するそうです。
どんな働き方でも、残業や夕方以降の会議など
 ということです。
ということです。ただし、時短勤務にすると手当や給与の面でどうしてもフルタイムより減少します。
前述した方は、色々悩み、職場や家族と相談し、フルタイムで4月から復帰するそうです。
どんな働き方でも、残業や夕方以降の会議など
業務時間外の対応が難しい状況や
子どもの病気などでの欠勤や早退等もあり得ます。
周囲の理解あっての仕事ですので、状況に甘んじることなく、
周囲の理解あっての仕事ですので、状況に甘んじることなく、
それぞれの仕事に努力を惜しまないこと、
加えて配慮してもらった時には感謝をしっかり伝えること で
で
 で
で周囲も応援してくれるようになると思います。
復帰後は時間的にもハードで、
復帰後は時間的にもハードで、
思ったように仕事ができないもどかしさもあるかもしれません。
私自身も、産後の復帰で仕事をやめようかと悩んだ一人です。
同じ職場の先輩や知り合いや友人などのワーキングママに相談したりして
同じ職場の先輩や知り合いや友人などのワーキングママに相談したりして
前向きになれた気がします。
各家庭、仕事、預け先などそれぞれ違います。
ママだけで頑張ろうとせず、皆で協力体制を取りながら、
各家庭、仕事、預け先などそれぞれ違います。
ママだけで頑張ろうとせず、皆で協力体制を取りながら、
仕事復帰の山をのりこえましょう

2023年01月17日
赤ちゃんと冬の夜の暖房
こんにちは しんしろ助産所です
寒い冬には暖房が欠かせませんね。
ただ、地域にもよりますが
夜には暖房を切って寝るという方が
多いのではないでしょうか。
では、生後間もない赤ちゃんが
いるとしたらどうでしょうか。
「夜の暖房はつけっぱなしにした方がいいの?」
「乾燥するからつけっぱなしはよくないの?」
と相談を受けることもよくあります。
ネットで調べると・・・
・夜は冷え込むのでつけっぱなしにして
温度を保った方がいい
・空気が乾燥したり、赤ちゃんが温まりすぎてしまう
ことがあるからつけっぱなしはよくない
・新生児期はつけっぱなしにするほうがいい
など、考え方はさまざまです。
確かに迷ってしまいますね
基本的には、普段大人が寝るときに
暖房を切って生活をしているのなら、
赤ちゃんがいても夜の暖房は必要ないと思います。
ただ、赤ちゃんが寝てくれない、
機嫌が悪い、体(背中やお腹)が冷えている
といったことがあれば必要かもしれません。
夜中も続けて暖房を使用する時は
●温度を低めに設定する
●加湿対策をする
●赤ちゃんの様子を確認する
睡眠、機嫌、体(お腹や背中)が汗ばんでいないかなど
●暖房器具を選ぶ
・換気が必要なファンヒーターや石油ストーブは避ける
・乾燥しやすいエアコンは加湿に注意する
・オイルヒーターは空気の乾燥が少ないが
電気代や時間はかかりがち
といったことに注意しましょう。
さまざまな考え方があるということは
決まった答えはないということなのかもしれません。
赤ちゃんの様子を見ながら
元気に過ごせる方法を考えてあげたいですね

寒い冬には暖房が欠かせませんね。
ただ、地域にもよりますが
夜には暖房を切って寝るという方が
多いのではないでしょうか。
では、生後間もない赤ちゃんが
いるとしたらどうでしょうか。
「夜の暖房はつけっぱなしにした方がいいの?」
「乾燥するからつけっぱなしはよくないの?」
と相談を受けることもよくあります。
ネットで調べると・・・
・夜は冷え込むのでつけっぱなしにして
温度を保った方がいい
・空気が乾燥したり、赤ちゃんが温まりすぎてしまう
ことがあるからつけっぱなしはよくない
・新生児期はつけっぱなしにするほうがいい
など、考え方はさまざまです。
確かに迷ってしまいますね

基本的には、普段大人が寝るときに
暖房を切って生活をしているのなら、
赤ちゃんがいても夜の暖房は必要ないと思います。
ただ、赤ちゃんが寝てくれない、
機嫌が悪い、体(背中やお腹)が冷えている
といったことがあれば必要かもしれません。
夜中も続けて暖房を使用する時は
●温度を低めに設定する
●加湿対策をする
●赤ちゃんの様子を確認する
睡眠、機嫌、体(お腹や背中)が汗ばんでいないかなど
●暖房器具を選ぶ
・換気が必要なファンヒーターや石油ストーブは避ける
・乾燥しやすいエアコンは加湿に注意する
・オイルヒーターは空気の乾燥が少ないが
電気代や時間はかかりがち
といったことに注意しましょう。
さまざまな考え方があるということは
決まった答えはないということなのかもしれません。
赤ちゃんの様子を見ながら
元気に過ごせる方法を考えてあげたいですね

2023年01月13日
赤ちゃんの体重
こんにちは しんしろ助産所です
赤ちゃんの体重は、成長のバロメーター
おおよそ生後1か月までに約1㎏増加し、


赤ちゃんの体重は、成長のバロメーター

おおよそ生後1か月までに約1㎏増加し、
1歳ごろには出生時の3倍になるといわれます。
ただすべての赤ちゃんが等しく成長していくわけではありません。
助産所にも体重や哺乳量の計測に赤ちゃんとママが来ますが、
「赤ちゃんの体重が思うように増えていない 」と
」と
不安を持っているママは多くみえます。
乳幼児には適切な体重増加の目安があり、
厚労省が出している発育曲線といわれるグラフが
母子手帳の中にものっています。
そのグラフの帯の中に全体の94%の子どもの値が入るので
全体の中でどのくらいの発育状況かがわかります。
我が子がどのくらいの所にいるかを
成長曲線と照らし合わせ適宜チェックするといいですね。
大人でも身長体重に差があるのと同様に
赤ちゃんでも大きい子もいれば小さめの子もいます。
低出生体重児や早産児では成長曲線の中に入っていなくても
その子なりに成長していれば順調に育っているといわれます。
(かかりつけの医師や病院の判断を仰いでくださいね)
ただすべての赤ちゃんが等しく成長していくわけではありません。
助産所にも体重や哺乳量の計測に赤ちゃんとママが来ますが、
「赤ちゃんの体重が思うように増えていない
 」と
」と不安を持っているママは多くみえます。
乳幼児には適切な体重増加の目安があり、
厚労省が出している発育曲線といわれるグラフが
母子手帳の中にものっています。
そのグラフの帯の中に全体の94%の子どもの値が入るので
全体の中でどのくらいの発育状況かがわかります。
我が子がどのくらいの所にいるかを
成長曲線と照らし合わせ適宜チェックするといいですね。
大人でも身長体重に差があるのと同様に
赤ちゃんでも大きい子もいれば小さめの子もいます。
低出生体重児や早産児では成長曲線の中に入っていなくても
その子なりに成長していれば順調に育っているといわれます。
(かかりつけの医師や病院の判断を仰いでくださいね)
ただし、今まで順調に増加していたのに、
急にグラフが横ばいになったり、
また体重が減少しているなどの場合には
かかりつけ医などに早めに相談しましょう
急にグラフが横ばいになったり、
また体重が減少しているなどの場合には
かかりつけ医などに早めに相談しましょう


2022年12月20日
ママだって休んでいい‼
こんにちは しんしろ助産所です
今年もあと十日余り。
一時保育に預けることに罪悪感を持つママもいますが、
実際疲れが蓄積してストレスがかかると
注意力が散漫していい結果にならなかったり 自分の状況を声に出すこと
自分の状況を声に出すこと
 寝たい、リフレッシュしたいなどの思いを伝えること
寝たい、リフレッシュしたいなどの思いを伝えること
 一人だけの時間を作ること
一人だけの時間を作ること
ママのニーズは人それぞれ、1時間でも一人の時間があれば、
読書、散歩、テレビをみるのもよし、
カフェでお茶してもいいし、布団に入って寝るのもよし
ママだって休むのは当然のこと
まずは第1歩踏み出してみましょう。

今年もあと十日余り。
寒さも厳しくなってきましたね。
年の瀬はなぜか気ぜわしい感じがします。
ママは毎日 家事に育児に仕事にと大忙し

朝から夜まで色々な予定が詰まっていて、あっという間の毎日

気づけば寝ちゃってたなんてこともあるのではないでしょうか。
たまにはゆっくり休みたいと思っても
たまにはゆっくり休みたいと思っても
「私はママなんだから頑張らないと…」
と自分を追い詰めていませんか?
特に未就園児の小さな子どもを持つママは、
なかなか時間をとることはできないと思いますが
短時間でもいいのでゆっくりできる時間をもつことは大切です

パパや家族にお願いできればいいのですが、
それが無理なら一時保育の利用もいいのでは??
実際疲れが蓄積してストレスがかかると
注意力が散漫していい結果にならなかったり
パパや子どもへきつい言葉をかけてしまったりなど
ママにとっても家族にとってもメリットはありません。
「ママは休んではいけない」と自分自身で
律している方も少なくありませんが
ママが無理して倒れたら元も子もありません。
家庭自体が回らなくなってしまいます。
まずは
ママにとっても家族にとってもメリットはありません。
「ママは休んではいけない」と自分自身で
律している方も少なくありませんが
ママが無理して倒れたら元も子もありません。
家庭自体が回らなくなってしまいます。
まずは
 自分の状況を声に出すこと
自分の状況を声に出すこと 寝たい、リフレッシュしたいなどの思いを伝えること
寝たい、リフレッシュしたいなどの思いを伝えること 一人だけの時間を作ること
一人だけの時間を作ることママのニーズは人それぞれ、1時間でも一人の時間があれば、
読書、散歩、テレビをみるのもよし、
カフェでお茶してもいいし、布団に入って寝るのもよし

ママだって休むのは当然のこと

まずは第1歩踏み出してみましょう。
2022年11月28日
おしゃぶりの消毒
こんにちは しんしろ助産所です
おしゃぶりをしている赤ちゃんを見ると愛らしい ですね。
ですね。
おしゃぶりは安心感を得られる効果があるため、
赤ちゃんがリラックスしたいときや不安な時に求めるといわれます。
たしかにぐずってどうしようもない時 などにおしゃぶりを与えると
などにおしゃぶりを与えると
おとなしくなることがあります
ママは一時的にせよ、ホッとできますね。
すべての赤ちゃんが使っているわけではありませんが、
おしゃぶりは赤ちゃんが直接口にするものなので、
衛生面を気にされるママは結構いらっしゃいます。
月齢が低い赤ちゃんは病気に対する免疫がないため、
口に入れるものは清潔にする必要 があります。
があります。
そのため哺乳瓶と同様におしゃぶりも消毒が必要です。
おしゃぶりを頻繁に使う赤ちゃんは
いつ消毒したらいいのか気になるところです。
基本的にはおしゃぶりを外したらその都度消毒、
手間がかかる場合には複数用意しておくのもいいでしょう。
消毒は哺乳瓶と同じ方法(煮沸、レンジ、薬液消毒など)で問題ありません。
目安としては離乳食を食べる6か月頃まではしっかり消毒しましょう。
可能なら1歳ごろまではこまめに消毒するのがベストです。
まずはママが一番実践しやすい方法を選んで行ってみてくださいね。


おしゃぶりをしている赤ちゃんを見ると愛らしい
 ですね。
ですね。おしゃぶりは安心感を得られる効果があるため、
赤ちゃんがリラックスしたいときや不安な時に求めるといわれます。
たしかにぐずってどうしようもない時
 などにおしゃぶりを与えると
などにおしゃぶりを与えるとおとなしくなることがあります

ママは一時的にせよ、ホッとできますね。
すべての赤ちゃんが使っているわけではありませんが、
おしゃぶりは赤ちゃんが直接口にするものなので、
衛生面を気にされるママは結構いらっしゃいます。
月齢が低い赤ちゃんは病気に対する免疫がないため、
口に入れるものは清潔にする必要
 があります。
があります。そのため哺乳瓶と同様におしゃぶりも消毒が必要です。
おしゃぶりを頻繁に使う赤ちゃんは
いつ消毒したらいいのか気になるところです。
基本的にはおしゃぶりを外したらその都度消毒、
手間がかかる場合には複数用意しておくのもいいでしょう。
消毒は哺乳瓶と同じ方法(煮沸、レンジ、薬液消毒など)で問題ありません。
目安としては離乳食を食べる6か月頃まではしっかり消毒しましょう。
可能なら1歳ごろまではこまめに消毒するのがベストです。
まずはママが一番実践しやすい方法を選んで行ってみてくださいね。