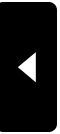2017年08月02日
上の子が下の子に手を出す原因とその対処法
こんにちは しんしろ助産所です
助産所にいると、
『下の子が生まれてから、上の子が下の子をたたいたりする 』
』
という話を耳にします。
厚労省の出産に関する統計から推測すると、
子どもの年齢差は2~3歳くらいが平均のようです。
(第2子の出産年齢の平均)- (第1子の出産年齢の平均)
この2~3歳は会話も徐々にできるようになってきますが、
別名『魔の2歳児 』とも言われ、イヤイヤ期真っただ中のな時期ですね。
』とも言われ、イヤイヤ期真っただ中のな時期ですね。
そんな頃に下の子が生まれると、はじめのうちは見ているだけだったのが、
慣れてくると、たたいたり、ひっかいたり
ふと見たら、寝ている下の子の上に馬乗りになっているなんてことも…
びっくりすることもしばしば
上の子は、下の子が生まれたことでとても複雑な気分
今までは、大好きなママを独占できて、おもちゃもテレビも本も全部自分のもの、
でも赤ちゃんが生まれてから、ママが赤ちゃんを抱っこしている、
おっぱいをあげてるなどみるとさびしくなるのは当たり前!!
ただ2~3歳では、下の子が生まれたことの理解がまだ十分にできないんですね。
お兄ちゃんやお姉ちゃんになることは、子どもからすると大きなストレス。
ママを取られたという思い、ママに注目してもらいたい、自分だけを見てほしい等の
複雑な感情が入り混じり、ストレスの矛先が赤ちゃんに向くのは仕方のないのことです。
“人間が生まれて初めて感じる嫉妬の対象は、兄弟である”という説もあるほど。
決して珍しいことではありません。
これらの行動に対して、頭ごなしに怒るのはNG
下の子をたたいているのを見ると焦りますが、
この場合は「たたくことはいけない!」と、行為を叱るのがポイント
「ひどい子だね」など、上の子を否定するような言動はやめましょう。
また、
1.上の子の感情を理解し、家族などに協力を得て、上の子と2人きりの時間を作る
2.大好きでとても大切な存在であることを、常日頃から伝え続ける
3.上の子のいいところを誉めて自信がつくようにする
4.下の子のお世話を一緒に手伝ってもらい、感謝する
等をしてみてください。
上の子を優先するだけで変化があることも・・・
ママが自分を見ていてくれるということがわかれば、気持ちが落ち着き、
下の子への攻撃も減り、兄弟としての愛情 が芽生えてきます。
が芽生えてきます。
どの子も大切でいとおしい存在
ママがその愛情を発信していれば、必ずわかってくれますよ。


助産所にいると、
『下の子が生まれてから、上の子が下の子をたたいたりする
 』
』という話を耳にします。
厚労省の出産に関する統計から推測すると、
子どもの年齢差は2~3歳くらいが平均のようです。
(第2子の出産年齢の平均)- (第1子の出産年齢の平均)
この2~3歳は会話も徐々にできるようになってきますが、
別名『魔の2歳児
 』とも言われ、イヤイヤ期真っただ中のな時期ですね。
』とも言われ、イヤイヤ期真っただ中のな時期ですね。そんな頃に下の子が生まれると、はじめのうちは見ているだけだったのが、
慣れてくると、たたいたり、ひっかいたり

ふと見たら、寝ている下の子の上に馬乗りになっているなんてことも…
びっくりすることもしばしば

上の子は、下の子が生まれたことでとても複雑な気分

今までは、大好きなママを独占できて、おもちゃもテレビも本も全部自分のもの、
でも赤ちゃんが生まれてから、ママが赤ちゃんを抱っこしている、
おっぱいをあげてるなどみるとさびしくなるのは当たり前!!
ただ2~3歳では、下の子が生まれたことの理解がまだ十分にできないんですね。
お兄ちゃんやお姉ちゃんになることは、子どもからすると大きなストレス。
ママを取られたという思い、ママに注目してもらいたい、自分だけを見てほしい等の
複雑な感情が入り混じり、ストレスの矛先が赤ちゃんに向くのは仕方のないのことです。
“人間が生まれて初めて感じる嫉妬の対象は、兄弟である”という説もあるほど。
決して珍しいことではありません。
これらの行動に対して、頭ごなしに怒るのはNG

下の子をたたいているのを見ると焦りますが、
この場合は「たたくことはいけない!」と、行為を叱るのがポイント

「ひどい子だね」など、上の子を否定するような言動はやめましょう。
また、
1.上の子の感情を理解し、家族などに協力を得て、上の子と2人きりの時間を作る
2.大好きでとても大切な存在であることを、常日頃から伝え続ける
3.上の子のいいところを誉めて自信がつくようにする
4.下の子のお世話を一緒に手伝ってもらい、感謝する
等をしてみてください。
上の子を優先するだけで変化があることも・・・

ママが自分を見ていてくれるということがわかれば、気持ちが落ち着き、
下の子への攻撃も減り、兄弟としての愛情
 が芽生えてきます。
が芽生えてきます。どの子も大切でいとおしい存在

ママがその愛情を発信していれば、必ずわかってくれますよ。

2017年08月01日
身近に潜む危険生物から子どもを守ろう
こんにちは しんしろ助産所です
私たちの日常には、
恐ろしい生物が 実はたくさんいます。
最近では毒ヘビやヒアリ、マダニが話題ですね。
子どもは危険生物の恐ろしさを知らないばかりか
好奇心旺盛なため、自ら近づいていくこともあります。
そのためにも親が普段から危険を教え、
気をつける必要がありますね。
<肌の露出を避ける>
アブは水場に多く存在します。
屋外プールでもよく見かけますね。
アブに刺されると急に猛烈な痛みを感じるため、
子どもが急に泣き出したら
アブに刺された可能性を考えましょう。
予防策としては、身体の露出部分をなくすこと。
紫外線対策を兼ねて 水着も布面積が大きいものにしましょう。
<草むらでのおしっこは要注意>
マダニは家庭内の「ダニ」とは別の、
山や茂みに生息する恐ろしい危険生物です。
何日にもわたって血を吸い続け、
吸い終わった時には元の何倍にも大きくなります。
登山やキャンプでは サンダルや露出の多い軽装を避け
防虫スプレーを使用しましょう。
柔らかい皮膚を好むため、
太ももや股を狙うことが多いようです。
無理にとると頭部だけ皮膚に残ってしまいます。
また、重症感染症を引きおこすことがあるため、
必ずそのまま病院に行きましょう。
<ジメジメが大好き>
ムカデは強力な毒を持っているため、
子どもが噛まれたら重症化する恐れがあります。
ムカデは湿った環境を好むため、
おふろの排水溝や脱衣所、
靴やスリッパの中などは要注意です。
着替えやタオルは必ず振ってから使用し、
靴やスリッパも中を確認してから
履く習慣をつけましょう。
<ヘビは毒をもっているという前提で>
マムシは日本の各地に生息し、
草むらや森林や水辺など、あらゆるところに潜んでいます。
マムシにかまれると 強い痛みと腫れ、しびれを伴います。
昔は毒がないと言われていたヤマカガシも
有毒ヘビだということがわかりました。
種類が判断できなくても 子どもがヘビにかまれた場合は
動かさないよう気をつけて病院へ行きましょう。
<死亡率の高いスズメバチ>
スズメバチはとても攻撃性が高いため、
近寄らない、刺激しないことが一番です。
スズメバチは攻撃前に「カチカチ」という威嚇音をだします。
「カチカチ」がきこえたら、そっとその場を離れましょう。
スズメバチに刺されると、体内に抗体ができるため、
2度目に刺された時にアナフィラキシーショックを起こし
命を落とすことがあります。
スズメバチに刺されたらすぐに病院に連れて行きましょう。
病院に勤めていた頃、5歳の子がマムシにかまれて
受診してきたことがありました。
マムシを見つけ、足で踏みつけたら
靴の上から親指をかまれたそうです。
親に言えず、我慢していましたが
様子がおかしいことに親が気づき、夜間救急を受診しました。
幸い大事には至りませんでしたが、
足は腫れ上がり、しばらく入院することになりました。
「次は踏んづけちゃだめだよ。
ヘビさんもきっと痛かったと思うよ。」というと、
「うん、次は絶対に棒でぶったたく!」
と言った姿が忘れられません
わんぱくで逞しいのは大いに結構ですが
子どもは予想をはるか超えたことを平気でします。
くれぐれも気をつけてくださいね!!
ちなみに「危険・有毒生物」という図鑑もあるようです。
夏休みに子どもと勉強するのも良いかもしれませんね

私たちの日常には、
恐ろしい生物が 実はたくさんいます。
最近では毒ヘビやヒアリ、マダニが話題ですね。
子どもは危険生物の恐ろしさを知らないばかりか
好奇心旺盛なため、自ら近づいていくこともあります。
そのためにも親が普段から危険を教え、
気をつける必要がありますね。
<肌の露出を避ける>
アブは水場に多く存在します。
屋外プールでもよく見かけますね。
アブに刺されると急に猛烈な痛みを感じるため、
子どもが急に泣き出したら
アブに刺された可能性を考えましょう。
予防策としては、身体の露出部分をなくすこと。
紫外線対策を兼ねて 水着も布面積が大きいものにしましょう。
<草むらでのおしっこは要注意>
マダニは家庭内の「ダニ」とは別の、
山や茂みに生息する恐ろしい危険生物です。
何日にもわたって血を吸い続け、
吸い終わった時には元の何倍にも大きくなります。
登山やキャンプでは サンダルや露出の多い軽装を避け
防虫スプレーを使用しましょう。
柔らかい皮膚を好むため、
太ももや股を狙うことが多いようです。
無理にとると頭部だけ皮膚に残ってしまいます。
また、重症感染症を引きおこすことがあるため、
必ずそのまま病院に行きましょう。
<ジメジメが大好き>
ムカデは強力な毒を持っているため、
子どもが噛まれたら重症化する恐れがあります。
ムカデは湿った環境を好むため、
おふろの排水溝や脱衣所、
靴やスリッパの中などは要注意です。
着替えやタオルは必ず振ってから使用し、
靴やスリッパも中を確認してから
履く習慣をつけましょう。
<ヘビは毒をもっているという前提で>
マムシは日本の各地に生息し、
草むらや森林や水辺など、あらゆるところに潜んでいます。
マムシにかまれると 強い痛みと腫れ、しびれを伴います。
昔は毒がないと言われていたヤマカガシも
有毒ヘビだということがわかりました。
種類が判断できなくても 子どもがヘビにかまれた場合は
動かさないよう気をつけて病院へ行きましょう。
<死亡率の高いスズメバチ>
スズメバチはとても攻撃性が高いため、
近寄らない、刺激しないことが一番です。
スズメバチは攻撃前に「カチカチ」という威嚇音をだします。
「カチカチ」がきこえたら、そっとその場を離れましょう。
スズメバチに刺されると、体内に抗体ができるため、
2度目に刺された時にアナフィラキシーショックを起こし
命を落とすことがあります。
スズメバチに刺されたらすぐに病院に連れて行きましょう。
病院に勤めていた頃、5歳の子がマムシにかまれて
受診してきたことがありました。
マムシを見つけ、足で踏みつけたら
靴の上から親指をかまれたそうです。
親に言えず、我慢していましたが
様子がおかしいことに親が気づき、夜間救急を受診しました。
幸い大事には至りませんでしたが、
足は腫れ上がり、しばらく入院することになりました。
「次は踏んづけちゃだめだよ。
ヘビさんもきっと痛かったと思うよ。」というと、
「うん、次は絶対に棒でぶったたく!」
と言った姿が忘れられません

わんぱくで逞しいのは大いに結構ですが
子どもは予想をはるか超えたことを平気でします。
くれぐれも気をつけてくださいね!!
ちなみに「危険・有毒生物」という図鑑もあるようです。
夏休みに子どもと勉強するのも良いかもしれませんね